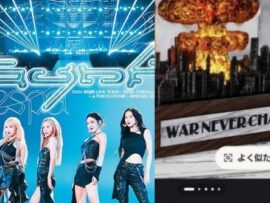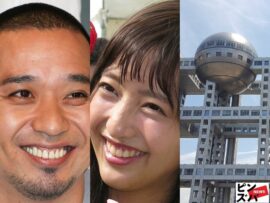月額2万3,053円——これは就労継続支援B型事業所で働く人たちが得られる、2023年度の全国平均工賃の月額です。報酬改定や工賃の算定方式の見直しもあり、前年よりも6,000円以上も増加しているものの、経済的に自立した暮らしを送るにはほど遠いのが現状です。
そのような背景の中、社会福祉法人チャレンジドらいふは日本財団からの助成を受けて、2024年3月、就労継続支援B型事業所の1つを廃止し、売上げで給与を払う一般事業所「ソーシャルファーム大崎」を、宮城県美里町に開設しました。
水耕栽培でホウレンソウを育てる植物工場で、利用者は一般雇用(社員)になります。社会保障費に頼らず給料を支払うことができる「脱福祉」型の就労施設となり、日本で初めての試みとなります。
それまで月額平均1万程度だった賃金(工賃)は、約9万円まで上がり、障害のある人たちの待遇改善につながっています。
工場の開設から約1年が経ち、そこで働く人たちにどのような変化が見られたのか。また、経営を継続する上で、いまどんな課題を抱えているのか。チャレンジドらいふの理事長・白石圭太郎(しらいし・けいたろう)さんにお話を伺います。
「利用者」から「社員」となり、働く人の意識に変化が生まれた
――「ソーシャルファーム大崎」を開設することになったとき、率直にどんなお気持ちでしたか。
白石さん(以下、敬称略):私はこれまで障害者の就労支援に携わってきましたが、長年、働くことができる障害のある人たちにチャンスがないことを疑問に思っていました。本当は一般就労も可能なはずなのに、多くの人が福祉施設で働く選択肢しか与えられていない。
ですから、「ソーシャルファーム大崎」を開設することで、障害のある人たちが働けて、活躍できることを証明できるのではないか、と思ったんです。
――「脱福祉」型就労という言葉が印象的です。
白石:厳密にいうと「脱公費」になります。「ソーシャルファーム大崎」で働いている皆さんも何らかの支援や配慮が必要で、そこには「福祉」は存在しています。ただ「公費」は存在しません(※)。
※就労継続支援は国や自治体が行う障害福祉サービスの一環であり、利用料がかかるが、原則9割は公費として国や自治体が負担。残り1割を利用者が負担する仕組みになっている
――開設にあたって、苦労した点はありますか?
白石:ここで働く社員は、もともとチャレンジドらいふが運営していたB型事業所の利用者の方たちなので、彼らを迎え入れる上での心配はありませんでした。どのようにサポートすればいいのかは、すでに分かっていましたので……。
ただ、ホウレンソウを水耕栽培するという面では苦労がありましたね。私も含め、誰もやったことがない作業ですし、農業すらしたことありませんでしたから。ですから、地元の農家さんにサポートしていただきながら、手探りで進めていきました。