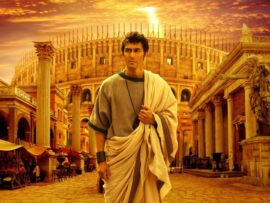JA(農業協同組合)といえば、農家の生活を支える組織というイメージを持つ方が多いでしょう。しかし、その内部では「不正販売」や「自爆営業」といった問題が蔓延しているという現実があります。今回は、元「日本農業新聞」記者の徹底取材に基づき、JA職員が抱える苦悩、そして組織の闇に迫ります。
過大なノルマが生む負の連鎖
JA職員の多くは、共済(保険)や信用(銀行)事業における厳しいノルマに追われています。この過大なノルマが、不正販売の温床となっているのです。ノルマを達成できない職員は、自ら不必要な共済に加入したり、知人に加入を頼み込み、その掛け金を肩代わりする「自爆営業」を強いられるケースも少なくありません。
自爆営業:職員もまた被害者
本来、組合員を守るべきJA職員が、なぜ不正販売に手を染めてしまうのでしょうか?その背景には、ノルマ未達成による経済的負担への恐怖があります。自爆営業は、職員自身の生活を圧迫するだけでなく、顧客への不利益な商品販売にもつながる深刻な問題です。
 JA職員の過大なノルマと自爆営業
JA職員の過大なノルマと自爆営業
組織ぐるみの隠蔽体質
JAとぴあ浜松の例では、約300人の職員がノルマ未達成の場合、不足分を補うために自ら共済商品を契約しています。一度契約した商品は解約できず、もし解約すれば実績から控除され、将来のノルマに上積みされるという悪循環に陥ります。このような状況下で、職員が不正販売に走ってしまうのも無理はないでしょう。
JA共済連の矛盾
驚くべきことに、これらの自爆営業の実態をJA自身も、共済商品の企画・普及を行うJA共済連も把握しています。しかし、JA共済連は「営利を目的としない」と主張するため、ノルマと自爆の存在を認めようとしないのです。
農家の未来を守るために
JAは本来、農家の生活を守るための組織です。しかし、現在のJAは、過大なノルマと自爆営業という負の連鎖に陥り、その理念からかけ離れた存在になりつつあります。この問題を解決するためには、JA内部の意識改革、そして透明性の確保が不可欠です。「食と農」を守るためにも、JA改革は喫緊の課題と言えるでしょう。
農業経済学者である山田一郎氏(仮名)は、「JAの抱える問題は、日本の農業の未来を左右する重要な課題です。組織全体の透明性を高め、組合員の声に真摯に耳を傾ける姿勢が求められています」と指摘しています。