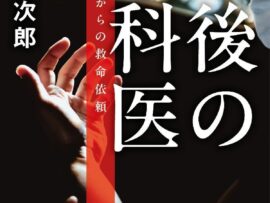成功するビジネスパーソンとそうでない人を分ける判断基準とは何でしょうか。早稲田大学名誉教授の内田和成氏が提唱するのは、客観的なデータや常識に囚われず、自身の「主観」を信じる重要性です。ユニ・チャーム創業者、高原慶一朗氏が、幹部の反対を押し切り「紙おむつ」市場に挑戦し大成功を収めた事例は、その典型と言えるでしょう。高原氏は無謀な賭けではなく、深い洞察と、自身の違和感を重視する主観的判断がありました。この記事では、客観情報が氾濫する現代で、いかに「直感」や「違和感」が正しい意思決定を導き出すのか、その秘訣を紐解きます。
バブル期の教訓:客観性よりも「違和感」を信じた経営者たち
少し古い話になりますが、バブル経済期には、多くの企業が不動産や株式投資に手を出し、その結果、多大な損失を被りました。当時、「いま買わなければ損」という市場の熱狂は、多くの人々を客観的な合理性から遠ざけました。しかし、そうした風潮に一切乗らず、自社を破綻の危機から救った経営者たちが存在します。彼らはバブル崩壊後も余計な損失を抱えることなく、厳しい時代を生き抜きました。
ある経営者は、なぜ投資話に乗らなかったのかという問いに対し、「なんかおかしい気がした」と、極めて感覚的な答えを返しました。銀行や証券会社、不動産会社の営業マンがこぞって「儲け話」を持ちかける状況に対し、彼は「本当に儲かるなら、なぜ自分でやらずに他人に勧めるのか」という強い違和感を抱いたのです。この主観的な「おかしい」という感覚こそが、彼をバブルの罠から守る最高のリスクヘッジとなったのです。
 思慮深いビジネスマンが重要な決断を下す様子
思慮深いビジネスマンが重要な決断を下す様子
「おかしい」という主観が最高の危機回避策に
この事例における「客観性」とは一体何だったのでしょうか。当時の世間一般では、株や不動産への投資が「合理的」であり、「常識」とされていました。投資の合理性を説く論理はいくらでも存在し、金融機関はその合理性を大衆に広く宣伝していました。しかし、その「客観的な論理」に従った多くの人々は、結局、破滅の道を辿ることになります。
一方、先の社長は、「おかしいのではないか」という自身の内から湧き出る違和感、すなわち主観的な感覚に基づいて、「いま投資話に乗るべきではない」と判断しました。重要なのは、彼がバブルの崩壊を予見していたわけではない点です。確たる根拠やロジックがあったわけではありません。それでも彼は、世間的な常識よりも「自分の主観」を信じ抜き、結果としてそれが最良の選択となりました。
もちろん、データや数値から合理的に考えてバブルの崩壊を予見することは不可能ではなかったという意見もあるでしょう。しかし、実際にそのような合理的な判断で危機を回避できた人がどれほどいたでしょうか。むしろ、自身の心に芽生えた「違和感」に真摯に向き合い、それをもとに意思決定を行ったこの経営者の話にこそ、現代社会が見落としがちな「主観」の重要性に関する深い教訓が隠されていると、内田教授は指摘します。
右脳的発想が導く「正しい選択」:新製品開発の例
こうした「感覚的な判断」は、ビジネスのさまざまな場面でしばしば「的を射ている」ことが証明されます。例えば、自社の開発部門が「画期的な新製品を発明した」と報告してきた際、経営者が感覚的に「何か違和感がある」と感じることがあります。社内では多くの肯定的な意見が飛び交い、一見するとヒットする可能性が高そうに思える状況でも、経営者にはどこか引っかかる点があるのです。
そこで市場調査を行わせると、実は過去に競合他社が似たような商品を投入し、鳴かず飛ばずの結果に終わっていた、というケースは少なくありません。もちろん、過去のデータだけで未来の成功を断定することはできません。アップル社のように、先行する失敗例があったにもかかわらず、それを覆すような革新的なヒット商品を次々と生み出している企業も存在します。
しかし、ここで強調したいのは、論理的思考だけでは到達し得なかった「正しい選択」を、「右脳的な発想」や「直感」が出発点となって導き出すことが多い、という事実です。自身の内なる声、つまり「主観」を大切にし、違和感を見過ごさない姿勢が、最終的にビジネスの成功に繋がる重要な鍵となるのです。
客観的なデータや市場の常識は重要ですが、それだけに依存することはリスクを伴います。ユニ・チャームの高原氏やバブル期を生き抜いた経営者の事例が示すように、成功するリーダーは自身の「直感」や「主観的な違和感」を深く信頼し、判断の基準としています。この「右脳的な発想」は、論理だけでは見えない真実を捉え、最も賢明な選択へと導きます。情報過多の時代だからこそ、自身の内なる声に耳を傾け、主観的な判断力を磨くことが、変化の激しいビジネス環境を生き抜くための不可欠な能力となるでしょう。