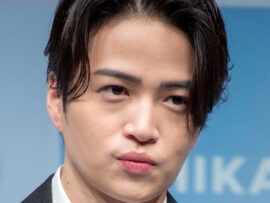ミャンマー中部を襲った大地震から1週間以上が経過しました。甚大な被害を受けたマンダレーでは、人々は壊れた家に戻ったり、がれきの撤去を始めたりと、少しずつ日常を取り戻そうと動き始めています。しかし、残された建物の安全確認は進んでおらず、二次災害の不安に怯える日々が続いています。
崩壊の爪痕深く、二次災害の恐怖
マンダレー在住のサンユさん(45歳)は、毎日新聞の取材に対し、街の現状を語ってくれました。発生当初の救助活動は落ち着きを見せつつあるものの、街の中心部以外では捜索はほとんど行われず、放置された建物からは死臭が漂い、ガス漏れによる火災も発生したといいます。
 ミャンマー中部マンダレーの地震被害の様子。重機を使った救助活動が行われている。
ミャンマー中部マンダレーの地震被害の様子。重機を使った救助活動が行われている。
中国、インド、ロシアなどからの国際救助隊も現地入りしていますが、人数や活動範囲は限られており、十分な支援が届いていないのが現状です。40度近くまで気温が上昇する日中、路上で避難生活を続ける人々も少なくありません。
サンユさんの家族は、一部損壊した自宅アパートにとどまっています。停電が続き不安な日々ですが、他に避難できる場所がないといいます。「余震で建物が崩れ、自分たちも巻き込まれるのではと怖い」と、サンユさんは二次災害への不安を口にしました。
復旧への期待と課題
サンユさんは、日本の地震対策の経験と技術に期待を寄せています。「日本は何度も大きな地震を経験して技術がある。街の復旧には技術的な支援が欠かせない」と訴えました。
地震工学の専門家である東京大学地震研究所の佐藤教授(仮名)は、「被災地の建物の安全確認は急務であり、耐震補強や建物の再建には、現地の状況に合わせた技術支援が不可欠です」と指摘しています。
軍事政権の対応と国際社会の懸念
軍事政権は3300人以上の死亡を確認していますが、北部ザガイン管区など軍政の支配が及ばない地域では被害状況の把握が難しく、実際の死者数はさらに多いとみられています。国軍による救助活動の妨害や支援物資の配布制限も報告されており、国際社会からの懸念が高まっています。国連人権高等弁務官事務所は、国軍が救援活動に当たる若者らを強制的に徴兵していると非難しました。
ミャンマーの地震災害は、人々の生活を奪うだけでなく、国の将来にも大きな影を落としています。国際社会の協力と支援が、一日も早い復興のために不可欠です。