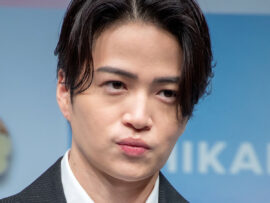首都直下地震は、いつ起きてもおかしくないと言われ続けている巨大地震です。この記事では、地学の専門家である鎌田浩毅京都大学名誉教授の著書『大人のための地学の教室』を参考に、首都圏の地震リスクについて分かりやすく解説します。地震のメカニズムを理解し、日頃から備えを万全にすることで、被害を最小限に抑えることができるはずです。
首都圏を囲むプレートと地震発生のメカニズム
首都圏は、北米プレートの下にフィリピン海プレートと太平洋プレートという2枚の海洋プレートが沈み込む、複雑な地質構造をしています。これらのプレート境界は地震の巣となり、常に地震発生のリスクを抱えています。2021年に発生した千葉県北西部地震は、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で起きた地震です。
 千葉県北西部地震の震源域
千葉県北西部地震の震源域
マグニチュード(M)5.9と比較的大きな地震でしたが、首都直下地震で想定されるM7.3と比較すると、エネルギーは約50分の1に過ぎません。マグニチュードが1上がるごとにエネルギーは32倍になるため、M7.3の地震はM5.9の地震とは比べ物にならないほどの破壊力を持つことになります。
活断層:都市部直下の脅威
首都直下地震は、プレート境界で発生する地震だけでなく、活断層が原因となる地震も含まれます。活断層とは、過去に繰り返し地震を起こし、今後も活動する可能性のある断層のことです。首都圏には「立川断層帯」など、多くの活断層が存在し、M6~7クラスの地震を引き起こす可能性が指摘されています。
日本全国には2000本以上の活断層があり、首都圏に限らず、いつどこで地震が発生してもおかしくない状況です。活断層による地震は、震源が都市部の直下になることが多く、甚大な被害をもたらす危険性があります。
関東大震災の教訓:火災への備え
1923年に発生した関東大震災では、約10万5000人の犠牲者のうち、9割が火災によって亡くなりました。「火災旋風」と呼ばれる巨大な炎の竜巻が発生し、多くの命を奪ったのです。地震による家屋の倒壊を防ぐことはもちろん、火災発生を防ぐ対策も重要です。
地震発生時には、エレベーターが停止し、閉じ込められるケースも少なくありません。2021年の千葉県北西部地震では、震度5強の揺れで7万台ものエレベーターが停止しました。首都直下地震のような大規模な地震が発生した場合、さらに多くのエレベーターが停止し、多くの人が閉じ込められる可能性があります。日頃からエレベーターの安全対策や情報伝達手段の確保が重要です。
専門家の声:地震への備えは日頃から
地震学者の佐藤一郎氏(仮名)は、「首都直下地震はいつ起きてもおかしくない状況です。日頃から家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、地震への備えを怠らないようにしましょう。また、避難経路の確認や家族との連絡方法なども事前に決めておくことが大切です。」と警鐘を鳴らしています。
まとめ:地震への備えで被害を最小限に
首都圏は、複数のプレート境界や活断層が存在し、常に地震の脅威にさらされています。千葉県北西部地震は、首都直下地震のリスクを改めて認識させる出来事となりました。地震のメカニズムを理解し、日頃から防災意識を高めることで、被害を最小限に抑えることができるでしょう。
この記事が、皆様の防災意識向上に少しでもお役に立てれば幸いです。