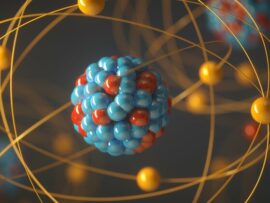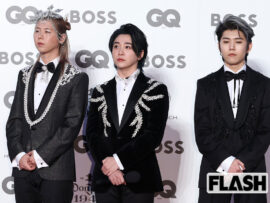家族が認知症と診断された時、深い悲しみと不安に襲われることでしょう。これからどうすればいいのか、どんな手続きが必要なのか、途方に暮れる方も少なくないはずです。この記事では、認知症と診断された直後にまず取り組むべき3つのステップを、専門家のアドバイスを交えながら分かりやすく解説します。安心してこれからの生活を設計していくためにも、ぜひご一読ください。
ステップ1:要介護認定の申請を最優先で行う
認知症と診断されたら、まず何よりも優先すべきは「要介護認定の申請」です。 介護保険サービスを受けるためには、この手続きが不可欠です。申請から認定までには約1ヶ月かかるため、いざサービスが必要になった時に慌てないよう、早めの申請がおすすめです。
なぜすぐに申請が必要?
「まだ介護サービスは必要ないから…」と申請を先延ばしにする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、介護が必要な状況は突然やってくることもあります。例えば、介護をしている方が急に入院した場合、認知症の方を一時的にショートステイに預ける必要があるかもしれません。 このような場合、要介護認定を受けていれば、ショートステイの費用負担は1割で済みますが、認定を受けていないと全額自己負担となってしまいます。
 alt
alt
介護支援専門員として長年活躍されている山田花子さん(仮名)は、「認知症の進行状況は予測できません。必要な時にスムーズにサービスを利用できるよう、診断後すぐに要介護認定の申請を行うことを強くお勧めします」と語っています。 早めの申請は、将来の不安を軽減するための重要な一歩と言えるでしょう。
ステップ2:情報収集と相談窓口の活用
要介護認定の申請と並行して、認知症に関する情報収集を行いましょう。地域包括支援センターや認知症相談窓口など、様々な相談窓口があります。これらの窓口では、介護に関する相談だけでなく、地域にある様々なサービスや支援制度の情報提供も受けられます。
適切な情報収集で不安を解消
インターネットで情報を探すこともできますが、情報が溢れかえっているため、どれが正しい情報なのか判断が難しい場合もあります。信頼できる相談窓口を活用することで、正確な情報を得ることができ、今後の見通しが立てやすくなります。
ステップ3:家族会議で今後の生活を設計
認知症と診断された後は、家族で今後の生活について話し合うことが大切です。介護の方法、住まいの環境、医療機関の選択など、様々な事柄について、家族全員で共有し、協力体制を築いていく必要があります。
家族の協力が重要
認知症介護は長期にわたる場合が多いため、介護者一人が全てを背負い込むのではなく、家族で役割分担をすることが重要です。 また、介護サービスの利用についても、家族でよく話し合って決めることが大切です。
認知症の診断は、ご家族にとって大きな転換期となるでしょう。しかし、適切な手続きと情報収集、そして家族の協力によって、安心して生活を送ることは可能です。この記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。