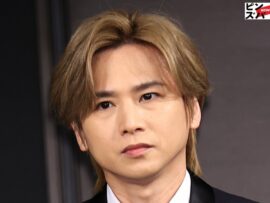笑いの授業…一体どんな授業?どんな効果があるの?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。今回は、長谷川博之教諭が実践するユニークな「笑いの授業」の様子と、その背後にある生徒一人ひとりの個性を尊重する教育理念に迫ります。誰もが安心して発言できる、活気あふれる教室作りのヒントが満載です!
笑いの授業で見えた!生徒中心の学び
長谷川教諭の笑いの授業では、生徒たちが自発的に立ち上がり、自分の考えを発表する姿が印象的でした。通常の授業は漢字スキルから始まるそうですが、この日は「指名なしスピーチ」からスタート。これは、他の生徒の発表を聞き、自分も話したいと思ったタイミングで自然と発言できる形式です。
 alt
alt
この「指名なしスピーチ」は、2週間ほど前から帰りの会でも実施されているとのこと。学級通信の内容について意見を共有することで、卒業前の最終仕上げとして表現力を磨いているそうです。
全員が輝く!「指名なし」の真価
「指名なし」だと、発言しない生徒が出てしまうのでは?という懸念も浮かびますが、長谷川教諭は、全員が発言の機会を持てるよう工夫を凝らしています。例えば、列ごとに発表を促すことで、発言内容が重複しても構わない雰囲気を作り出しています。
従来の「挙手・指名」方式では、どうしても「正解」が重視されがちです。しかし、長谷川教諭は「正解を出さなくていい」と生徒たちに繰り返し伝えています。正解の確認はテストで行えば良い、授業ではもっと深い学びを追求したい、という強い信念があるからです。
授業は「正解探し」じゃない!一人ひとりの考えを尊重
国語の授業において「正解は一つではない」と語る長谷川教諭。生徒たちは「自分はこう思うけど、みんなはどうかな?」という気持ちで発言しています。もちろん、口頭での発表だけが全てではありません。パソコンに自分の考えを入力することも立派な表現方法として認められています。
多様な表現方法を認める
人前で話すのが苦手な生徒、緊張しやすい生徒もいます。だからこそ、長谷川教諭は「ここぞという時に発言できればOK」「パソコン入力も価値がある」と生徒たちに伝えています。実際、授業中に一度も発言しない生徒も、パソコンで自分の考えをまとめていました。
著名な教育学者、山田先生(仮名)も「多様な表現方法を認めることは、生徒の自己肯定感を高める上で非常に重要です」と述べています。
まとめ:個性を尊重する学びで、未来を切り開く!
長谷川教諭の笑いの授業は、単に「笑い」をテーマにした授業ではありませんでした。生徒一人ひとりの個性を尊重し、安心して発言できる環境を作ることで、深い学びへと繋げる、そんな教育理念が根底にあると感じました。