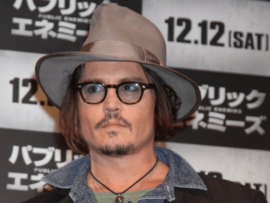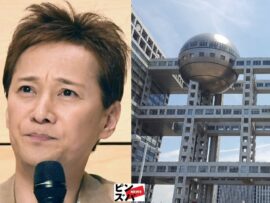お客様として当然の権利を守る「正当なクレーム」と、度を超えた要求や迷惑行為にあたる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。その境界線はどこにあるのでしょうか?本記事では、カスハラ防止条例施行後の現状を踏まえ、カスハラと正当なクレームの違い、そして「嫌なお客様」にならないためのスマートなクレームの伝え方をご紹介します。
カスハラ防止条例とは?その影響と課題
2025年4月1日、東京都、北海道、群馬県、三重県桑名市で「カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。愛知県、三重県も条例制定の方針を固めており、他県でも検討が進むなど、全国的な広がりを見せています。
カスハラは社会問題となっていましたが、「お客様は神様」という意識や、明確な基準の欠如から対策が遅れていました。この条例は、カスハラに対する認識を統一し、企業の対応を後押しする狙いがあります。
 カスハラに関するニュース記事の画像
カスハラに関するニュース記事の画像
東洋大学の桐生正幸教授は、これまで曖昧だったカスハラの定義を明確化した意義を強調しています。多くのカスハラは暴行・脅迫といった明確な犯罪ではなく、大声での抗議などグレーゾーンに位置していました。条例によって一定の基準が示されたことは、法制化への第一歩と言えるでしょう。
日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事は、条例の有効性を指摘しつつも、自治体ごとの対応の違いに言及しています。東京都や北海道では罰則規定がない一方、桑名市では悪質なケースで氏名公表の可能性があるなど、対応にばらつきが見られます。抑止力という観点からは、より踏み込んだ条例が効果的かもしれません。
カスハラと正当なクレーム:その違いを見極める
東京都はカスハラの代表的な例をガイドラインで示していますが、正当なクレームとの境界線は依然として分かりにくい部分も残ります。一体、どこで線引きすれば良いのでしょうか?
例えば、「料理に髪の毛が入っていた」というケース。これは正当なクレームと言えるでしょう。しかし、同じ状況でも、店員への暴言や理不尽な要求(返金だけでなく慰謝料も要求するなど)を伴う場合はカスハラとみなされる可能性があります。
重要なのは、問題解決のために、冷静かつ丁寧に伝えることです。感情的にならず、事実を明確に伝えましょう。
スマートなクレームの伝え方:嫌なお客様にならないために
では、どのようにクレームを伝えれば良いのでしょうか? 具体的なポイントは以下の通りです。
問題点の明確化
- 何が問題だったのかを具体的に伝えましょう。「料理がまずかった」ではなく、「味が濃すぎた」「生焼けだった」など、具体的に指摘することで、改善に繋がります。
感情的な言葉は避ける
- 「最悪だ」「二度と来ない」といった感情的な言葉は避け、冷静に事実を伝えましょう。
敬意を払う
- どんなに不満があっても、相手への敬意は忘れずに。丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
代替案の提示
- 可能であれば、代替案を提示するのも効果的です。「返金してほしい」だけでなく、「別の料理に変更してほしい」といった提案も検討してみましょう。
まとめ:お客様として、そして社会の一員として
カスハラ防止条例は、お客様と企業、双方にとってより良い環境を作るための第一歩です。冷静な判断力と適切な行動を心がけ、気持ちの良いコミュニケーションを築きましょう。そして、美味しい食事を心から楽しむために、正しいクレームの知識を身につけておきましょう。