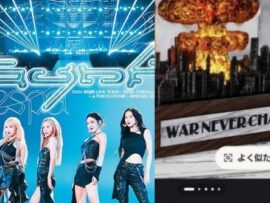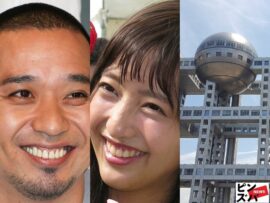サウナブームの終焉を告げるニュースが増えてきました。果たして本当にサウナは「オワコン」なのでしょうか?この記事では、サウナブームの現状をデータに基づいて分析し、人気の秘訣を探ります。ブームに陰りが見えているとはいえ、サウナの魅力は決して色褪せていません。
サウナブームの軌跡と現状
サウナブームの火付け役となったのは、ドラマ「サ道」や著名人のサウナ体験談、そしてSNSでの拡散でしょう。「サウナー」「ととのう」といった言葉が浸透し、2021年には「ととのう」が新語・流行語大賞にノミネートされるほどの一大ムーブメントとなりました。健康志向の高まりも追い風となり、従来の「オジサンの嗜好」というイメージを覆し、若者層にもサウナ人気が波及しました。各施設も「サ飯」の充実やイベント開催など、顧客体験の向上に力を入れてきました。コロナ禍においても、時間予約制や個室サウナの導入など、柔軟な対応策が講じられました。「サウナバス」や「サ旅」といった新しいサービスも登場し、話題を呼びました。
 サウナを楽しむ人々
サウナを楽しむ人々
しかし、ブームの陰で変化も起きています。一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所(日本サウナ総研)の調査によると、サウナ利用者はコロナ禍前の2020年度と比べて、2021年度以降は約1000万人減少しました。この数値は2024年度時点でも回復していません。サウナ総研は、コロナ禍による生活様式の変化、特に時間予約制や個室サウナの導入などが影響したと分析しています。
サウナ愛好家たちの動向
日本サウナ総研は、利用頻度に基づきサウナ利用者を「ヘビーサウナー(月4回以上)」「ミドルサウナー(月1回~3回)」「ライトサウナー(年1回から2~3か月に1回)」に分類し、その推移を調査しました。結果、ヘビー・ミドルサウナー層はコロナ禍後も利用頻度は微減にとどまりましたが、ライトサウナー層の減少が顕著でした。つまり、ブームに乗ってサウナに興味を持った層が離れていったことがわかります。
利用頻度が減少した理由についても調査が行われました。ヘビー・ミドルサウナー層では、施設の利用料金や混雑度合いよりも、付帯施設の機能変化が大きな要因となっていることが明らかになりました。例えば、以前は提供されていたサービスがなくなったり、施設の雰囲気が変わったりしたことが、彼らの足が遠のく原因となっているようです。「サウナ専門家の山田さん(仮名)」は、「コアなサウナーにとって、サウナ室だけでなく、水風呂の温度や外気浴スペースの環境なども重要な要素。これらの変化が、利用頻度に影響を与えている可能性がある」と指摘しています。
サウナ人気の継続に向けて
サウナブームは落ち着きを見せているものの、サウナそのものの魅力は変わりません。心身のリフレッシュ効果やコミュニティ形成の場としての役割など、サウナは現代社会において重要な役割を担っています。今後、サウナ人気を継続させるためには、ライトサウナー層を取り込む工夫が不可欠です。例えば、初心者向けのサウナ講座やイベント開催、多様なニーズに対応した施設づくりなどが考えられます。また、サウナ文化の魅力を発信し、理解を深めることも重要です。
まとめ
サウナブームは一過性のものだったのでしょうか?データを見る限り、ブームの勢いは落ち着きを見せているのは事実です。しかし、コアなサウナー層は依然としてサウナを楽しんでおり、サウナ文化は根付いています。今後、サウナの魅力を再発見し、新たな層を取り込むことで、サウナ人気は再び盛り上がりを見せる可能性を秘めていると言えるでしょう。