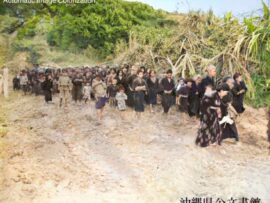日本の食卓に欠かせないお米。近年、その価格が高騰し続けています。スーパーの棚に並ぶ米袋の値段を見て、ため息をつく方も多いのではないでしょうか。今回は、高騰する米価の現状、韓国からの米輸入増加の背景、そして日本の農業政策の課題について深く掘り下げていきます。
米価高騰の現状と家計への影響
近年の米価は、上昇の一途を辿っています。5キロの平均価格は、年末年始には3571円だったのが、4月には4217円にまで跳ね上がり、15週連続で最高値を更新しています。家計への影響も大きく、食費全体を圧迫する要因となっています。
 alt
alt
外食産業やコンビニエンスストアも、この米価高騰の影響を受けています。牛丼チェーンの松屋は、牛めしの並盛を30円値上げ。ローソンでは、弁当のご飯の量を減らし、おかずを増量するなどの対応策をとっています。
韓国米輸入増加の背景:品質向上と価格競争力
米価高騰を受け、韓国から米を輸入する動きが活発化しています。SNS上では、韓国で安く米を購入したという投稿も見られます。韓国農協インターナショナルによると、日本への米輸出量は増加傾向にあり、1990年の統計開始以来、初めてのこととなっています。
キャノングローバル戦略研究所の農業政策専門家、山下氏(仮名)は、「韓国米の品質向上は目覚ましく、アメリカの一部のスーパーでは日本米に代わって韓国米が並ぶケースもある」と指摘しています。価格競争力に加え、品質の向上も、韓国米の人気を後押ししていると言えるでしょう。
日本の農業政策の課題:過剰な介入と競争力の低下
長年、日本では減反政策によって米の生産調整が行われてきました。値崩れを防ぐ狙いでしたが、2018年の廃止後も、転作への補助金など、実質的な生産調整は続いています。
橋下徹氏は、こうした日本の農業政策について、「政府の過剰な介入」を批判しています。「本来、価格は需要と供給で決まるべき。政府が介入することで、市場メカニズムが歪められている」と指摘し、競争にさらされることで品質向上を目指す韓国の農業政策との違いを強調しています。

さらに、株式会社の農業参入規制や、個人農家保護の弊害として、農業の高齢化と生産量の減少を挙げています。「自由な競争と、若い世代の参入を促す政策が必要」と提言しています。 食料安全保障の観点からも、日本の農業の競争力強化は喫緊の課題と言えるでしょう。
まとめ:持続可能な農業への転換を
米価高騰は、日本の食卓、そして農業の未来に大きな影を落としています。韓国米の輸入増加は、消費者の家計防衛策として注目されていますが、同時に、日本の農業政策の課題を浮き彫りにしています。持続可能な農業を実現するためには、生産性向上、競争力強化、そして若い世代の育成など、多角的なアプローチが必要不可欠です。