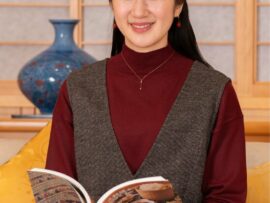いまシリコンバレーをはじめ、世界中で古代哲学「ストイシズム」の教えが注目され、その実践的な知恵が広く求められています。日本でも、ストイックな生き方を通じて困難を乗り越える方法を説く書籍『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)が刊行され、大きな反響を呼んでいます。禁欲や自己規律を通じてより良い生を送るという逆説的な教えは、現代社会における様々な課題、特に人間関係の複雑さに対処するための有効な手段となり得ます。本稿では、日常生活で直面する人間関係の悩みを取り上げ、ストイシズムの観点からどのように考え、行動すべきかを探ります。
マウントをとる人の行動とその背景
小学校に通う息子さんが、クラスメイトとの関係に悩んでいるという話は、多くの親にとって他人事ではないでしょう。特定の友達を標的にし、「そんなこともできないのか」「早くしろよ」といった言葉で相手をからかい、見下すような態度をとる子ども。周囲が注意しても聞く耳を持たない、いわゆる「ジャイアンタイプ」の子どもは、残念ながらどの時代、どの場所にも存在します。彼らは、相手を見下すことで一時的に自分を優位に立たせようとしますが、その行動の根底には、真の強さではなく、周囲からの承認や評価が得られないことへの不安があるのかもしれません。このような行動は子どもの世界に限らず、大人の社会においても見受けられる人間関係の課題の一つです。先生に相談するなどの一時的な解決策では、問題の根本的な解消には繋がりにくい場合もあります。
コントロール可能な領域に焦点を当てるストイシズム
では、このような難しい人間関係に直面したとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。ここで、ストイシズムの哲学が提供する重要な知恵が役立ちます。ストイシズムの中心的な教えの一つに、「自分がコントロールできることと、そうでないことを見分け、コントロールできることに全力を尽くせ」というものがあります。他人や外部の環境は、私たちの意のままになるものではありません。彼らがどのように考え、感じ、行動するかを私たちが直接コントロールすることは不可能です。「もっとこうなってくれたらいいのに」と他人の行動に悩んでも、それは自分では変えられない領域に心を乱されているだけです。
それに対し、私たち自身がコントロールできる領域は明確に存在します。それは、自分自身の思考、感情、そして行動です。私たちは、外部からの出来事や他人の言動に対して、どのように反応するかを自分で選択することができます。
 人間関係の悩みやストレスについて考え込む人物。ストイシズムの実践で心の平穏を得るイメージ。
人間関係の悩みやストレスについて考え込む人物。ストイシズムの実践で心の平穏を得るイメージ。
ストイックな対処法:自分の反応を選ぶ
息子さんの例に戻れば、バカにしたような言い方をするクラスメイトに対し、「そういう言い方はやめてほしい」と自分の意見を伝えることは、自分の行動としてコントロール可能です。あるいは、相手の言葉に過剰に心を乱されることなく、「イヤなヤツの言うことは気にする必要はない」と受け流すこともまた、自分の内面的な反応としてコントロール可能な選択です。相手が何を言ってこようと、それによって自分の幸福度が直接的に左右されるわけではありません。自分は自分の価値観に基づき、幸せになるための行動を選択することができるはずです。ただし、感情に任せて相手と同じように意地悪な言葉を返したり、報復したりすることは、ストイシズムの教えとは異なります。そのような行動は、誰にとっても建設的ではなく、自分自身の心の平穏をも乱す結果となります。
セネカの教え:すべての人への思いやり
ストイックな哲学者は、困難な状況においても内面の平静と美徳を追求することを説きました。ストア派の代表的な哲学者の一人であるセネカは、特に「つねに優しくあれ(思いやりを持て)」という教えを強調しました。彼の言葉は、『ルキリウスに宛てた道徳書簡集』の中で以下のように述べられています。
「思いやりは、身近な人に横柄になることを許さず、身近な人を貪ることを許さない。思いやりがあると、すべての人に対する言葉と行動と感情が穏やかで優しいものになる。」
クラスでマウントをとる子には、確かにこの「思いやり」が欠けているように見えるかもしれません。しかし、だからといって、こちらまで思いやりをなくす必要はありません。大人になってからも、不快な言動をとる相手に出会うことは少なくありません。そうした相手と同じレベルで言い返したり、感情的に無視したりするだけでは、根本的な解決には至りません。ストイシズムの実践者は、たとえ相手が難しい人物であったとしても、すべての人に対して穏やかさと優しさを持ちつつ、同時に相手のネガティブな行動によって自分自身の心が乱されないよう、内面の強さを保つことを目指します。
日常生活での実践と学び
息子さんと、こうしたストイシズムの考え方について話し合うことは、彼が将来、様々な人間関係の課題に立ち向かうための貴重な学びとなります。大人でも実践が難しい哲学ですが、このような機会があるたびに、ストイシズムの知恵を借りながら対話を重ねることで、困難に揺るがない強い心を育むことができるかもしれません。筆者自身も、ストイシズムの教えを完全に体得したわけではありません。日々の生活の中で、人間関係や予期せぬ出来事に直面するたびに、ストイックな考え方を思い出し、コントロールできることに集中し、思いやりを持って対応できるよう、常に学び、実践していくことが重要だと感じています。
参考文献
- ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳『STOIC 人生の教科書ストイシズム』
- ヤフーニュース掲載記事 (Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/31ed104c4d596ff0c0e8f3c8bfa503e35ba26eaf)