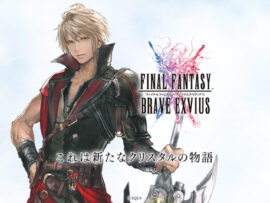公立高校の入試制度が大きく変わるかもしれない。これまで多くの都道府県で採用されてきた「単願制」が見直され、複数の高校を志願できる「デジタル併願制」の導入が検討されている。この記事では、デジタル併願制の概要、メリット・デメリット、そして今後の展望について詳しく解説する。
デジタル併願制とは?
デジタル併願制とは、生徒が複数の高校を志願し、入試の点数や内申点、面接、部活動の成果などを基に、デジタル技術を活用したアルゴリズムで自動的に合格校を割り振る仕組みだ。志望順位を事前に登録し、アルゴリズムによって順位付けされた後、合格基準を満たした高校の中から最も上位の学校に合格となる。
 alt
alt
デジタル併願制導入のメリット
デジタル併願制には、いくつかのメリットが期待されている。まず、生徒にとって、複数の高校を受験できるため、進路選択の幅が広がる。単願制では、不合格になった場合に費用が高額な私立高校に進学せざるを得ない家庭もあったが、併願制によって公立高校への進学機会が増える可能性がある。
また、単願制では、志望校のランクを下げて受験する生徒も少なくなく、実力よりも低いレベルの高校に進学するケースもあった。デジタル併願制では、実力に見合った高校に進学できる可能性が高まる。
さらに、学校側にとっても、デジタル処理によって事務作業の負担が軽減されるというメリットがある。海外では既に導入事例も多く、効率的な入試運営が実現されている。
デジタル併願制導入のデメリットと課題
一方、デジタル併願制には懸念点も存在する。最大の懸念は、生徒や学校の序列化が進む可能性だ。生徒が順位付けされることで、偏差値重視の傾向が強まり、学校の専門性や校風を考慮した進路選択が難しくなる恐れがある。
教育評論家の山田花子氏(仮名)は、「デジタル併願制は、生徒の多様な才能や個性を無視し、画一的な評価基準に基づいて選別を行うシステムです。これでは、真の教育改革とは言えません」と警鐘を鳴らす。
また、アルゴリズムの透明性や公平性も重要な課題だ。どのような基準で順位付けが行われるのか、アルゴリズムに偏りがないかなど、入試の公平性を確保するための対策が必要となる。
alt
今後の展望
文部科学省は、デジタル併願制の導入に向けて、メリット・デメリットを慎重に検討していく方針だ。公立高校入試の実施主体は都道府県であるため、制度導入は各都道府県の判断に委ねられる。
愛知県や福岡県など、既に複数校を受験できる制度を導入している自治体もある。これらの事例を参考にしながら、より良い入試制度の構築を目指していくことが重要となるだろう。
デジタル併願制は、公立高校の入試制度を大きく変える可能性を秘めている。生徒の進路選択の幅を広げ、教育の質向上に繋がる一方で、序列化や公平性といった課題も抱えている。今後の議論の行方を見守りたい。