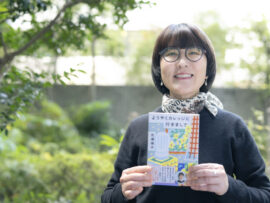大阪・関西万博は、連日多くの来場者で賑わいをみせています。しかし、その一方で、総額13兆円にも上る巨額の関連費用に対する懸念の声も上がっています。会場建設費の増大や広域インフラ整備など、本当に「万博の名の下」にこれほどの投資が必要なのでしょうか?この記事では、その経済合理性と未来への影響について深く掘り下げていきます。
巨額投資の根拠はどこに?「万博関連事業」の定義に潜む矛盾
2021年、大阪府、大阪市、関西広域連合、そして経済団体が国に提出した「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)関連事業に関する要望」という文書があります。この文書では、会場周辺のインフラ整備だけでなく、関西一円、さらには中国・四国地方にまで及ぶ道路、港湾、鉄道などの整備事業が「万博関連事業」として挙げられています。
 alt
alt
批判の高まる巨額の費用について、維新関係者や一部メディアは「万博とは直接関係のない事業費が含まれている」と反論していますが、この要望書の存在は、その主張の矛盾を露呈しています。自ら「万博のため」と定義した事業を、批判されると「別物」と主張するのは、責任転嫁に他なりません。
健活10ダンスも万博関連事業?費用肥大化の背景にある政治的思惑
さらに、大阪府庁への取材で確認したところ、「健活10ダンス」も万博関連事業に含まれていることが判明しました。このように、当初の想定をはるかに超える事業が「万博」の名の下に次々と追加され、費用が膨れ上がっているのです。
万博は、国際イベントというよりも、巨額の公共事業予算を獲得するための「口実」として利用されている可能性が否めません。少なくとも13兆円の投資を前提に、多くの企業が既に動き出している現状を考えると、その影響は計り知れません。
未来への投資?それとも壮大な無駄遣い?経済合理性の欠如
要望書では、万博を「ポストコロナにおける成長・発展の起爆剤」と謳っていますが、その具体的な根拠は示されていません。「やってみなはれ」の精神論や「未来社会の実験場」といった抽象的なスローガンだけでは、巨額投資の正当性を説明するには不十分です。
マッシアーニ論文が指摘するメガイベントの落とし穴
経済効果評価の専門家であるジャン=バティスト・マッシアーニ氏は、メガイベントの評価において、代替効果や機会費用といった経済合理性を測る視点が不可欠であると指摘しています(注1)。しかし、万博計画では、これらの視点が完全に欠落していると言わざるを得ません。
(注1) ジャン=バティスト・マッシアーニ著『このイベントは経済にどれだけ利益をもたらすのか?──経済効果評価のためのチェックリストとミラノ万博2015への適用』(2020年、ミラノ・ビコッカ大学)
万博推進派は、バラ色の未来像だけを描き、実現のためにあらゆる分野での公的支援を要求しています。しかし、その実態は、具体的な根拠に基づかない「願望リスト」に過ぎないのではないでしょうか。
13兆円の投資は未来への希望となるか?それとも負の遺産となるか?
大阪・関西万博は、未来への投資となる大きな可能性を秘めています。しかし、現状のままでは、巨額の負債と無駄なインフラだけが残る可能性も否定できません。真に未来を見据えた万博とするためには、経済合理性に基づいた計画の見直しと、透明性の高い情報公開が不可欠です。私たち国民一人ひとりが、この巨大プロジェクトの行く末を真剣に見つめ、未来への責任を果たしていく必要があるのではないでしょうか。