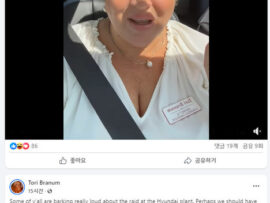ガソリン価格の高騰が家計を圧迫する中、ガソリン税の減税を求める声が大きくなっています。一方で、気候変動対策の観点から増税を主張する意見も。果たして、日本のガソリン税は国際的に見て本当に安いのでしょうか?そして、私たちにとって最適な選択とは?この記事では、ガソリン税をめぐる議論を多角的に分析し、未来への道筋を探ります。
ガソリン税をめぐる現状
2025年4月24日放送の報道番組「news23」(TBS系)に出演した東京大学の斎藤幸平准教授は、日本のガソリン税の安さを指摘し、暫定税率の引き上げを提言しました。政府はガソリン価格の抑制策として1リットルあたり10円の引き下げを決定しましたが、野党からは25.1円の暫定税率廃止を求める声が上がっています。
 ガソリン価格の表示
ガソリン価格の表示
斎藤准教授は、ドイツのガソリン価格が1リットルあたり約250円であることを例に挙げ、日本のガソリン税が国際的に見て低いことを強調。気候変動対策の観点からも、ガソリン消費を促進するような減税ではなく、暫定税率を炭素税のような恒久的なものとして引き上げるべきだと主張しました。
国際比較でみる日本のガソリン税
ガソリンに対する税負担率を国際比較すると、日本は42.6%、アメリカは52.4%、フランスは53.0%、ドイツは53.9%となっています。これらの数値からも、日本のガソリン税負担率が低いことが分かります。
例えば、食生活アドバイザーの山田花子さん(仮名)は、「環境問題を考えると、ガソリン税を引き上げて電気自動車への移行を促進する政策が必要だと思います」と述べています。
減税か増税か、難しい選択
番組キャスターからは、地方における車の必要性や物価高騰による家計への負担を考慮すべきだという意見も出されました。斎藤准教授は、電気代補助金やガソリン補助金のような一時的な対策ではなく、長期的な産業転換につながる政策が必要だと反論。エネルギー需給や電気自動車に関する議論を同時に進めるべきだと主張しました。
街頭インタビューでは、若い世代を中心にガソリン価格よりも生活必需品への支援を求める声が聞かれました。生活のひっ迫感の中で、ガソリン税の議論は優先順位が低いと感じている人も多いようです。
未来を見据えた選択を
ガソリン税の減税は、短期的な家計負担の軽減にはつながるかもしれませんが、長期的な視点で考えると、気候変動対策や持続可能な社会の実現には逆行する可能性があります。
環境ジャーナリストの田中一郎さん(仮名)は、「ガソリン税の増税分を再生可能エネルギーの開発や公共交通機関の整備に充てることで、より良い未来を築けるはずです」と提言しています。
私たちの未来のために、どのような選択をするべきか、真剣に考える必要があるのではないでしょうか。
まとめ
ガソリン税をめぐる議論は、短期的な経済効果と長期的な環境問題、そして私たちの生活のバランスをどうとるべきかという難しい課題を突きつけています。一人ひとりが問題意識を持ち、未来を見据えた選択をすることが重要です。