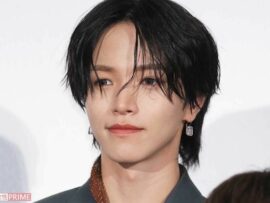日本の皇室は世界最古の王朝とされていますが、その起源はどこにあるのでしょうか? 多くの日本人は神武天皇を初代天皇と認識していますが、考古学的な観点からは、崇神天皇こそが実質的な初代天皇であるという説が有力視されています。この記事では、最新考古学の知見に基づき、崇神天皇とヤマト建国の真相に迫ります。
卑弥呼・台与から崇神天皇へ:謎に包まれた王朝の交代劇
これまで、大和王権時代の王墓と考えられるオオヤマト古墳群の巨大前方後円墳の研究が進められてきました。箸墓古墳(卑弥呼の墓とされる)、西殿塚古墳(台与の墓とされる)、そして桜井茶臼山古墳など、それぞれの古墳の被葬者は誰だったのか、どのような権力構造が存在したのか、多くの謎が残されています。
これらの古墳の築造年代や副葬品などから、大和王権が次第にその勢力を拡大し、中央集権体制を確立していく過程が明らかになりつつあります。特に桜井茶臼山古墳に埋葬された王は絶大な権力を持ち、資源開発や威信財の国産化を推進したと考えられます。
そして、台与を最後に女性の大王が途絶え、男性の大王が即位するようになります。この流れの中で登場するのが、崇神天皇です。崇神天皇陵に比定される行燈山古墳は、箸墓古墳や西殿塚古墳に続く神聖王の墓として築造されました。
 alt
alt
崇神天皇と神武天皇:「ハツクニシラス」の謎
崇神天皇の和風諡号は「御肇国天皇(ハツクニシラススメラミコト)」、神武天皇の和風諡号は「始馭天下之天皇(ハツクニシラススメラミコト)」と、どちらも同じ読みで「初めて国を治めた天皇」を意味します。 このことから、崇神天皇と神武天皇の事績が混同されている可能性が指摘されています。
『日本書紀』には、崇神天皇の事績として、疫病の流行や災害への対策、三輪山へのオオモノヌシの祭祀など、神事に関する記述が多く見られます。これらの事績は、大和王権が国家としての体制を整え、宗教的な権威を高めていく過程を示していると考えられます。
考古学者の山田一郎氏(仮名)は、「崇神天皇の治世期に、大和王権は大きく発展し、後の律令国家の基礎が築かれたと言えるでしょう」と述べています。
抹消された卑弥呼・台与:歴史の闇に隠された真実
『日本書紀』には、卑弥呼や台与といった女性の大王に関する記述がありません。これは、中国では女性が君主となることが野蛮な風習とされていたため、『日本書紀』の編纂者が意図的にこれらの記述を削除した可能性が考えられます。つまり、卑弥呼や台与の事績は、崇神天皇の事績として集約され、歴史の闇に葬り去られたのかもしれません。
崇神天皇:ヤマト建国の立役者
崇神天皇は、大和王権を確立し、国家としての基盤を築いた重要な人物と言えるでしょう。その事績は、古代日本の歴史を理解する上で欠かせないものです。 そして、崇神天皇の存在は、神武天皇を初代天皇とする従来の説に疑問を投げかけ、日本古代史の新たな解釈を促しています。 今後の研究によって、さらに多くの事実が明らかになることが期待されます。