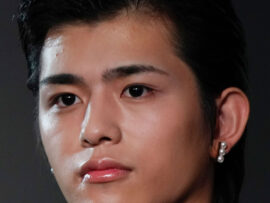大阪・関西万博のシンボル、壮大な「大屋根リング」。万博閉幕後、その未来はどうなるのでしょうか? 344億円もの巨費を投じて建設されたこの巨大構造物ですが、解体後の再利用は難航しているようです。この記事では、大屋根リングの再利用を取り巻く課題と、その未来への模索について探っていきます。
集成材の特性と再利用の壁
大屋根リングの主要材料は集成材です。薄い板を接着剤で張り合わせた集成材は、万博期間中の強度を確保するためにJAS規格に適合させて製造されています。しかし、この規格が長期使用における再利用の壁となっているのです。建築基準法の専門家である山田一郎氏(仮名)は、「JAS規格は特定の期間における強度を保証するもので、その期間を超えた使用については安全性を担保できません。そのため、既存の建築物への転用は非常に難しい」と指摘します。
 alt
alt
大阪府木材連合会が主催した説明会でも、この点が大きな課題として浮き彫りになりました。参加企業からは、再利用の可能性を探る声があがる一方で、JAS規格の壁を前に具体的な活用策を見出すのは困難な状況です。結果として、現状では全体の1割程度の再利用にとどまる見込みとなっています。
モニュメントとしての保存と新たな可能性
地元住民からは、大屋根リング全体をモニュメントとして保存してほしいという声も上がっています。しかし、適切な防腐処理を施さない限り、数年で劣化が始まってしまうとのこと。長期保存には、太陽の塔のように継続的なメンテナンスが必要不可欠です。
alt
そこで、大阪府木材連合会は、ベンチや机、日よけなど、JAS規格に縛られない小規模な活用方法を提案しています。また、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会での活用も視野に入れ、国土交通省に打診しているとのこと。
環境への配慮と未来への希望
約6万本分の木材を使用した大屋根リング。その再利用は、環境問題への意識の高まりからも重要な課題です。木材のリサイクル活用を推進するNPO法人「木の未来」代表の佐藤花子氏(仮名)は、「大屋根リングの再利用は、循環型社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。木材の特性を活かした新たな活用方法の開発が期待されます」と語ります。
大阪府木材連合会の取り組みは、大屋根リングの未来への希望を繋ぐ重要な一歩と言えるでしょう。万博の象徴が新たな形で活用され、未来へと受け継がれていくことを期待したいものです。