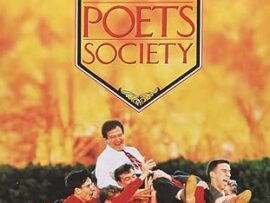食料品への消費税負担軽減は、家計にとって大きな関心事です。立憲民主党が提案する食料品消費税率1年間ゼロ%案に対し、国民民主党の玉木雄一郎代表はX(旧Twitter)で「効果は限定的」と指摘し、議論を呼んでいます。この記事では、玉木代表の主張と、食料品消費税減税をめぐる現状について詳しく解説します。
玉木代表、食料品消費税ゼロに異議
玉木代表は、立憲民主党の提案する食料品消費税率1年間ゼロ%案について、その効果に疑問を呈しています。同氏は独自の試算に基づき、1年間の減税効果は1人あたり年間約2万円強にとどまると指摘。国民民主党が主張する所得税の控除額「103万円の壁」を178万円に引き上げる方が、減税効果は大きいと主張しています。
 alt
alt
所得税減税vs消費税減税:どちらが効果的?
玉木代表は、所得税減税の方が低所得者層への恩恵が少ないという指摘に対し、2万円程度の現金給付や国民民主党が提唱する再生可能エネルギー賦課金徴収の一時停止で対応可能だと反論。これらの施策は、食料品消費税率ゼロ%化よりも迅速かつ広範囲に家計負担軽減効果をもたらすと主張しています。
消費税法改正の手間と効果のバランス
玉木代表は、消費税法改正の手間と1年間限定の消費税減税の効果を比較し、後者は限定的だと結論付けています。消費税率の変更は、事業者にとってシステム改修などの負担が生じる可能性があり、その効果が一時的なものであれば、費用対効果の面で疑問が残ると言えるでしょう。「食料品価格高騰対策」として効果的な政策とは何か、議論の余地があります。
立憲民主党の「給付付き税額控除」との整合性にも疑問
玉木氏は、立憲民主党が提出している給付付き税額控除法案には賛同できるところも多いとしながらも、同法案に含まれる「消費税の税率の一律化」と、複数税率を前提とした食料品の軽減税率ゼロ%との整合性について疑問を呈しています。これについては、立憲民主党からの更なる説明が必要だと述べています。
専門家の見解
架空の経済学者、山田太郎教授は、「消費税減税は短期的には家計負担軽減効果があるものの、持続可能性が課題。長期的には、経済成長を促す構造改革と組み合わせることが重要」と指摘しています。
今後の議論の行方
食料品消費税減税は、家計負担軽減の観点から重要な政策課題です。玉木代表の指摘は、今後の議論に一石を投じるものとなりそうです。国民生活への影響を考慮しつつ、効果的かつ持続可能な政策が求められています。