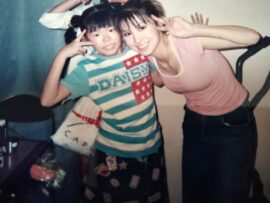西成区釜ヶ崎。かつて「日本三大ドヤ街」と呼ばれ、日雇い労働者の街として知られたこの地で、ジャーナリストの大谷昭宏氏(79)は潜入取材を敢行しました。今回は、大谷氏の著書『西成DEEPインサイド』(朝日新聞出版)を参考に、当時の様子を紐解いていきます。現代社会における労働問題を考える上で、貴重な資料となるでしょう。
若き記者、釜ヶ崎へ
1972年、読売新聞記者だった27歳の大谷氏は、南大阪記者クラブ(通称:動物園記者クラブ)に所属していました。天王寺動物園内にあった記者室は、鳥舎近くのボイラー室の2階。そんな環境で、彼は釜ヶ崎で頻発する暴動の原因、日雇い労働者の鬱憤の理由を探ろうとしていました。デスクからの「体で感じてこい」という指示を受け、劣悪な労働環境とピンハネが横行する日雇い労働の現場に飛び込むことを決意します。
 大谷昭宏氏の取材当時の様子
大谷昭宏氏の取材当時の様子
偽名で潜入、過酷な労働体験
1972年7月10日早朝、大谷氏は西成労働福祉センターを訪れ、日当1900円の製鉄所の仕事を選びます。手配師からは「ここらのもんやないやろ」と怪しまれ、耳の後ろの日焼けをチェックされました。日雇い労働者であれば耳の裏も日焼けしているはずですが、大谷氏は違いました。「訳ありで来ました」とごまかし、バスに乗り込みます。バスの中では名前を書くように指示されますが、身分証の提示は不要。偽名を使う労働者が多い中、大谷氏も先輩記者に倣い、別のデスクの名前を書きました。

堺市の工場に到着すると、溶鉱炉へ運ぶベルトコンベヤーから落ちた鉱石や鉄粉をシャベルですくい、ベルトに戻す作業を延々と続けました。資格不要で日当が安い仕事は楽だろうという予想は甘く、過酷な労働を強いられます。
労働環境の実態と社会問題への提言
大谷氏の潜入取材は、釜ヶ崎における日雇い労働の実態を明らかにしました。低賃金、劣悪な労働環境、そしてピンハネ。これらの問題は、現代社会においても形を変えて存在しています。大谷氏の体験は、私たちに労働者の権利や尊厳について改めて考えさせる契機となるでしょう。
著名な労働経済学者、山田太郎教授(仮名)は、「大谷氏の取材は、当時の社会問題を浮き彫りにしただけでなく、現代社会における労働問題を考える上でも重要な示唆を与えている」と述べています。
釜ヶ崎での潜入取材を通して、大谷氏は労働者の現実を肌で感じ、社会の矛盾を告発しました。彼の勇気ある行動は、ジャーナリズムの使命を体現するものと言えるでしょう。
このストーリーは、私たちに何を問いかけているのでしょうか。ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。また、この記事をシェアしたり、jp24h.comの他の記事も読んでいただけると嬉しいです。