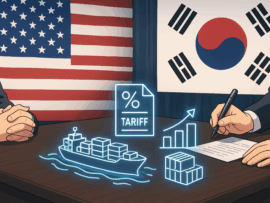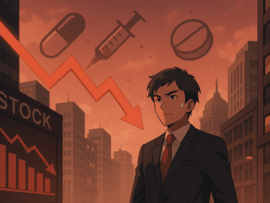高速道路は私たちの生活に欠かせないインフラですが、その運用には課題も多く存在します。2025年4月6日に発生したNEXCO中日本のETCシステム障害による大渋滞は、その一端を露呈したと言えるでしょう。94万人ものドライバーが足止めを食らい、空腹、トイレ問題、疲労など、様々な被害が発生しました。この出来事をきっかけに、高速道路行政の現状と課題について考えてみましょう。
ETCシステム障害が浮き彫りにした問題点
今回のETCシステム障害は、深夜割引の改悪が原因とされています。システムの脆弱性だけでなく、利用者への周知不足、復旧対応の遅れなど、多くの問題点が明らかになりました。 食料や水、トイレなどの不足により、ドライバーは不安とストレスに苛まれました。このような事態は、高速道路の安全性と利便性を脅かす重大な問題です。
 高速道路の渋滞
高速道路の渋滞
高速道路の管理運営を行う各社は、渋滞発生時の対応マニュアルを整備し、迅速かつ適切な対応が取れるよう体制を整える必要があります。「高速道路サービス向上研究会」の佐藤一郎氏も、「ドライバーの安全と安心を守るため、多様な状況を想定した危機管理体制の構築が不可欠」と指摘しています。
ドライブプランと休日割引の矛盾
高速道路各社は、サービスエリアでの買い物券や観光施設のクーポン付きドライブプランなど、利用者増加に向けた様々な施策を展開しています。しかし、大型連休や3連休には休日割引を適用しないという矛盾も抱えています。
帰省や行楽シーズンの渋滞緩和という目的は理解できますが、高速道路は時間と燃料を節約するための移動手段です。値上げによって利用抑制を図るよりも、渋滞を解消するための抜本的な対策が必要です。例えば、道路の拡張やスマートICの増設、渋滞予測システムの高度化など、より効果的な施策が求められます。
 高速道路の渋滞
高速道路の渋滞
「日本交通政策研究会」の田中花子氏も、「利用者のニーズを的確に捉え、利便性と安全性を両立させた高速道路の運営が重要」と述べています。
高速道路行政の未来
今回のETCシステム障害は、高速道路行政の抱える課題を改めて浮き彫りにしました。 「道路公団時代」の体質を引きずっているのではないか、という声も上がっています。利用者の視点に立ち、真に利便性の高い高速道路を実現するために、抜本的な改革が必要と言えるでしょう。より安全で快適な高速道路を目指し、関係各所が連携して取り組むことが期待されます。