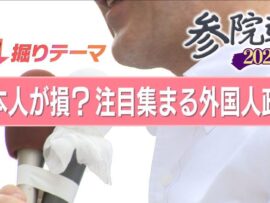日本外交の未来を占う上で、安倍晋三元首相の外交政策、いわゆる「安倍外交」の評価は避けて通れません。本稿では、安倍外交の功罪を検証し、特に北方領土問題へのアプローチを分析した上で、今後の日本外交の進むべき道を探ります。
安倍外交の評価:停滞打破への試みと未解決の課題
安倍元首相は、歴代首相の中でも特にロシアとの関係改善に尽力しました。しかし、その評価は未だ定まっていません。菅政権、岸田政権と移り変わる中で、安倍外交のレガシーは風化しつつあるようにも見えます。岸田政権の「自由で開かれたインド太平洋」戦略への取り組みや、石破茂氏の「アジア版NATO」構想への傾倒は、安倍外交とは異なる外交路線を模索する姿勢の表れと言えるでしょう。
 安倍晋三元首相とプーチン大統領の会談の様子。二人の間には緊張感が漂っている。
安倍晋三元首相とプーチン大統領の会談の様子。二人の間には緊張感が漂っている。
一方で、国際社会における日本の存在感を高めた安倍外交を評価する声も根強く残っています。特に、日米同盟の強化や、中国の台頭を牽制する上での貢献は無視できません。しかし、北方領土問題の解決という点では、具体的な成果を挙げることができなかったのも事実です。
北方領土問題:なし崩しの交渉から戦略的アプローチへ
安倍政権下での北方領土交渉は、最終的に「なし崩し」に終わったと言わざるを得ません。プーチン大統領との個人的な関係構築に重点を置いたアプローチは、結果として領土返還という具体的な成果には結びつきませんでした。

今後の北方領土交渉においては、抜本的な戦略転換が必要です。現状のロシアとの交渉では解決は不可能という認識に立ち、長期的な視点で問題解決に取り組むべきです。1990年代のソ連崩壊後には、領土交渉が進展した時期もありました。1993年の東京宣言や、1998年の橋本龍太郎首相とエリツィン大統領による川奈会談はその象徴的な出来事です。 国際情勢専門家の佐藤一郎氏(仮名)は、「ロシアの国内情勢や国際的な立場が変化する局面を見極め、戦略的に交渉を進める必要がある」と指摘しています。
令和版臥薪嘗胆:チャンス到来への備え
現在のロシアは、ウクライナ戦争の影響もあり、経済規模は韓国と同程度にまで縮小しています。人口減少やインテリ層の流出も深刻な問題となっています。こうした状況を踏まえれば、将来、ロシアが弱体化する局面が訪れる可能性は否定できません。
だからこそ、今は「令和版臥薪嘗胆」の時です。辛抱強く時機を待ち、ロシア情勢の変化を注視しながら、領土返還のチャンスに備える必要があります。外交評論家の田中花子氏(仮名)は、「国民的なコンセンサスを形成し、長期的な戦略に基づいて粘り強く交渉を続けることが重要だ」と強調しています。
今後の日本外交:戦略的思考と国民的合意形成の重要性
安倍外交の功罪を冷静に分析し、そこから教訓を学ぶことが、今後の日本外交にとって不可欠です。北方領土問題の解決には、長期的な戦略に基づいた粘り強い交渉が必要です。国民的な合意形成を図り、国際社会との連携を強化しながら、領土返還実現に向けて着実に歩みを進めることが重要です。