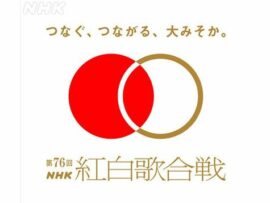与那国島に生息する固有種ヨナグニシュウダに、ヘビ真菌症(SFD)の感染が確認されました。これは国内初の野生ヘビにおけるSFD感染例であり、希少種の保全に深刻な影響を与える可能性があります。この記事では、SFDの脅威、感染状況、今後の対策について詳しく解説します。
ヘビ真菌症(SFD)とは?致死率の高い危険な感染症
ヘビ真菌症(SFD)は、カビが原因でヘビの皮膚に異常を引き起こす感染症です。感染すると皮膚の壊死や脱皮不全が起こり、致死率は約40%と非常に高く、世界中でヘビの個体数減少の要因の一つとされています。SFDは人への感染はありませんが、生態系への影響が懸念されています。
 ヨナグニシュウダの皮膚。脱皮不全で皮が浮いたり、うろこが変色したりしている。
ヨナグニシュウダの皮膚。脱皮不全で皮が浮いたり、うろこが変色したりしている。
国内初の野生ヘビにおけるSFD感染確認:ヨナグニシュウダへの影響
2019年に捕獲・冷凍保存されていたヨナグニシュウダを麻布大学の宇根有美名誉教授が分析した結果、2024年にSFDの原因となるカビの遺伝子が検出されました。ヨナグニシュウダは環境省レッドリストで絶滅危惧種に指定されている希少種であり、今回の感染確認は種の存続に深刻な影を落とします。
他の地域への感染拡大の懸念
SFDはヨナグニシュウダだけでなく、石垣島のサキシマスジオや、長野県伊那市のジムグリの抜け殻からも確認されています。宇根名誉教授によると、感染疑いの報告は十数例に上るといいます。これらは、SFDが既に国内の様々な地域に広がっている可能性を示唆しており、早急な対策が必要です。
専門家の声
爬虫類専門の獣医師、佐藤一郎氏(仮名)は、「SFDの感染拡大は、日本のヘビの生態系に深刻な影響を与える可能性がある。特に、島嶼部に生息する固有種は、感染症に対する抵抗力が弱いため、より大きな被害を受ける恐れがある。」と警鐘を鳴らしています。
今後の対策と調査
宇根名誉教授は、2023年6月にも与那国島と石垣島で現地調査を行う予定です。この調査を通して、感染経路の解明や感染拡大の防止策を検討することが期待されます。国内では2021年に輸入されたペットのヘビでSFD感染が初めて報告されましたが、野生の在来種への感染経路は未だ不明です。
私たちにできること
SFDは人への感染はありませんが、ペットのヘビを飼育している場合は、感染予防に注意を払い、異常が見られた場合は速やかに獣医師に相談することが重要です。また、野生生物の保護に関心を持つことで、SFDのような感染症の脅威から生態系を守ることに繋がるでしょう。
まとめ
ヨナグニシュウダへのSFD感染確認は、日本の生物多様性にとって大きな危機です。今後の調査と対策によって、感染拡大を防ぎ、希少種の保全に繋げることが求められます。