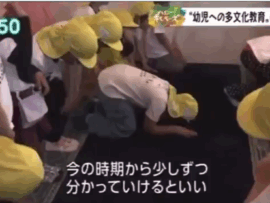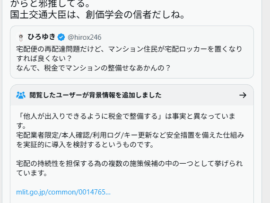[ad_1]
1996年に日本で初めて病識(自分が病気であるという認識)のない精神疾患患者を説得して医療につなげる「精神障害者移送サービス」を立ち上げた、(株)トキワ精神保健事務所の所長、押川剛さん。
メンタルヘルス患者のリアルな問題点を描き出し、シリーズ累計210万部超えとなっているコミック『 「子供を殺してください」という親たち 』(バンチコミックス)に続き、原作を担当した新シリーズ『 それでも、親を愛する子供たち 』では、児童養護施設を舞台に、子供たちの過酷な現実を提示している。
なぜ押川さんは漫画での発信を続けるのか。日本の精神保健福祉と児童福祉に共通する問題点とは。日本の将来に関わる深刻な課題に向かい続ける押川さんに話を聞いた。(全3回の1回目/ 続きを読む )
◆◆◆
コロナ禍で患者の地域移行が加速した
──押川さんには2021年の新型コロナウイルス感染症のパンデミック中にもオンラインでお話を伺いました。コロナ禍ではお仕事も大変だったのではないでしょうか。
押川剛さん(以下、押川) そうですね。トキワ精神保健事務所は連日、「困っているんです、なんとかしてください」という相談の電話が鳴りっぱなしでした。でも当時は、どんなに「助けてあげたい」「力になってあげたい」と思っても、病院も行政もシャットアウトで、コロナ禍以前から継続的に支援している患者さん以外には、手を差し伸べることもできない状況でした。
──5月9日に発売となった『「子供を殺してください」という親たち』の最新刊( 第17巻#82 )でも、継続的にサポートされていた患者さんに十分なケアができなくなった状況が克明に描かれていました。
押川 相馬仁志のケース ですね。コロナ禍ではやっと信頼関係が構築できていた患者さんにも3分、5分という短い面会しか許されなくなりました。仁志をはじめ、病識のない患者さんたちは、アクリル板など挟まない通常の距離感での人間的なコミュニケーションによって寛解状態を保つことができていたのですが、コミュニケーションが断絶されたせいで、みな一様に状況が悪化しました。
──仁志さんのケースでは、症状がよくなったとは思えないのに、他の支援団体が介入して病院を退院させていました。そんな本人にとってもまわりにとってもよいとは思えない状況が進んだのも、コロナ禍の影響ですか?
押川 もともと進められていた精神疾患を有する患者の地域移行が、コロナ禍で加速したということです。
近年は「地域共生社会」の号令のもと、精神科病院や大規模な障害者施設が否定され、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する、つまり、地域のなかのグループホームや一般住宅での暮らしへ移行するように、転換が図られてきました。これが、コロナ禍によって「密を避ける」という理由でうまい具合に地域移行・地域定着が進められたのです。
また、厚生労働省の診療報酬改定によって、地域移行・地域定着に向けた重点的な支援である「退院」を推進する病院や入所施設に加算がつくことになったことも、アウトリーチ化を推進させました。
さらに、この退院加算を狙って、対応困難な患者を本人や家族との関係調整もせずに一方的に退院させて報酬をかせぐ支援団体も増えてきたのです。以前は、引きこもりやニートの自立支援をうたって対象者を拉致し、施設に監禁する「引き出し屋」という業者が多くいましたが、本人の自立支援としての最善を無視して退院させる「逆引き出し屋」のような支援団体が増えてきたことによって、状況は本当に悪くなったと感じています。
先日もある精神科病院のソーシャルワーカーから聞いたのですが、支援団体の助言を信じて施設に入所した患者さんが、預貯金を搾取されたり虐待を受けたりして、「病院のほうが安心だ。再入院したい」と戻ってくるケースが増えているそうです。生活困窮者を狙った「貧困ビジネス」とまったく同じことが、障害者の分野でも起きているのです。
[ad_2]
Source link