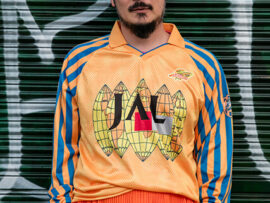ゴールデンウィークの沖縄県・尖閣諸島で、緊迫の事態が発生した。中国海警局のヘリコプターが、尖閣諸島周辺の領空に一時侵入し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進したのだ。中国海警局のヘリコプターによる領空侵犯は初となる。日本政府は中国政府に抗議したが、中国海警局は、日本の民間航空機が領空に不法侵入したため、警告して追い払ったと主張している。
尖閣諸島周辺では、中国船による領海侵犯も常態化している。先日も機関砲を搭載した中国海警局の船2隻が、尖閣諸島付近の領海に侵入し、そのまま領海内にとどまり、巡視船が領海の外に出るよう警告した。
中国による軍事活動の活性化については、4月に中谷防衛大臣が同盟国などと連携し、対応すると発言している。しかし相次ぐ領空侵犯や領海侵入を受けて、SNS上では政府の対応をめぐり、強気な対応を求める声も出ている。
連日のように押し寄せる中国船に、どのような対応を取るのが適切なのか。『ABEMA Prime』では、現場経験のある元海上保安庁職員とともに考えた。
■領海侵犯した船からヘリが…4度目の領空侵犯に
5月3日12時すぎ、中国海警局の船4隻(機関砲搭載)が、尖閣諸島周辺の日本領海に侵入した。そして12時21分、中国船の甲板からヘリが飛び立ち領空侵犯。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進し、ヘリは15分後に着艦した。海警局のヘリが領空に侵入するのは初めてだ。そして13時ごろまでに、4隻は領海外へ出た。
海上保安庁で40年以上勤務し、尖閣諸島周辺の警備を指揮した経験も持つ、元・第3管区 海上保安本部長の遠山純司氏は、「中国は尖閣に対するプレッシャーをかけ続けているが、そのかけ方は非常に巧妙だ。島を奪取しようとする直接的な行動ではなく、国際法的には問題のない、領海のギリギリ外側にある接続水域を回り、たまに領海に突っかかり『権益がある』とアピールしている」。
5月3日の事案については、「ヘリのケースは初めてだが、これまで中国海警局の船が領海に入ってきたときも、同様の主張をしていた。尖閣の領海内で操業する日本の漁船を“不法操業”だとして、『正当な法執行を行った』という理由を付けている」と解説する。
一部報道によると、民間航空機は海上保安庁から引き返すよう言われ、魚釣島周辺の手前で引き返したとの情報もある。「航空法に基づいて、航空機の安全確保のために警告が発せられた。ただ漁船もそうだが、中国側を刺激して、付け入る隙を与える行為をやることが、長期的に日本の国益を見たときにベストかは疑問だ」。
これまでも幾度となくトラブルが起きてきた。「その都度、日本はアクションを起こしてきた。民主党政権時に尖閣3島を国有化してから、中国海警局の船が恒常的に回り始めた」。3月24日には、中国海警局の船2隻が連続侵入し、92時間8分にわたり領海内にとどまった。これには「日本漁船が領海内で操業し、それにつきまとった結果だ。きっかけを日本が与えていることには注目すべきだろう」との見方を示す。
日本は、どのような態度をとるべきなのだろう。「国民は『日本政府は何もしていない』という印象を持っているが、実は数十隻の巡視船が絶えず厳重に監視している。指一本触れさせていない平時には何も言わなくていい。ことさらに相手を刺激する行動に出るのはどうなのか」。