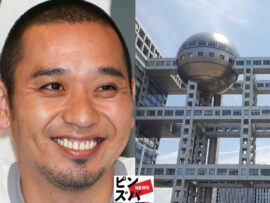5年に1度行われる年金制度改革。16日に閣議決定された「年金制度改革関連法案」は、これまで自民党内部で反対の声が根強く、当初予定していた時期から大幅に遅れて国会に提出されます。老後を支える年金は、今回の法案が成立するとどう変わるのでしょうか。
■法案の柱「106万円の壁」撤廃へ
今回の制度改革の柱の一つは、パートやアルバイトなどで働く短時間労働者が厚生年金に入りやすくして、これらの人が将来受けとる年金額を増やすことです。
現在、学生以外のパートやアルバイトなどの人たちが厚生年金に加入するには、
・従業員数51人以上の企業で、
・週20時間以上働き、
・賃金が月8万8000円以上(年収がおよそ106万円以上)
という条件をすべて満たす必要があります。
今回の制度改革が行われれば、これらのうち、企業規模と年収の条件を将来的に撤廃し、多くの短時間労働者が厚生年金に入りやすくなります。まず収入の条件、いわゆる「106万円の壁」については、最低賃金の上昇もあり、2026年をめどに撤廃される見込みです。また、企業規模については2027年10月からは従業員36人以上の企業…などと段階的に対象を広げ、10年後の2035年10月には、従業員に関する企業規模要件が完全に撤廃されます。厚生労働省によりますと、収入と企業規模の条件撤廃により、将来的にあわせて180万人が新たに厚生年金に加入する見込みだということです。
■パートの働き控え対策も
そもそもアルバイトやパートの人などは、加入する年金の種類が国民年金なので、将来受けとる年金額が低いのが課題です。社員と同じく厚生年金に加入すれば、年金額が増えるほか、国民年金の場合は毎月の年金保険料を全額自分で負担するのに対して、厚生年金では年金保険料の半額を企業側が負担してくれます。
一方で、たとえば会社員の夫の扶養家族であるパート主婦の場合、年金保険料を納めなくて良い立場(第3号被保険者といいます)ですが、厚生年金に加入することになれば年金保険料を納めることになります。保険料を納めることで手取りが減るのを避けるため、現在、パートの主婦は月給が8万8000円(年収約106万円)の「壁」を超えないよう働く時間を調整する実態があります。
今回の改正には、この「働き控え」を防ぐため、保険料の負担を軽くする特別措置も盛り込まれました。年金保険料は労働者と企業が半額ずつ負担していますが、3年間に限り、労働者の負担分を減らす仕組みが設けられました。企業は、たとえば8万8000円の労働者の場合、保険料の負担割合を労働者25%企業75%に変更できるなどというものです。これに伴う企業への負担も考慮して、半額以上の負担をした企業には補助金も出るということです。