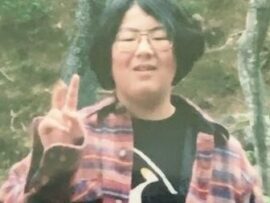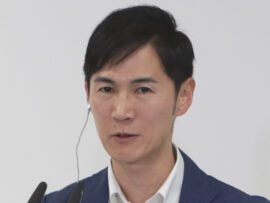NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。「黄表紙」の祖である戯作者で、浮世絵師の恋川春町(こいかわ・はるまち)もその一人だ。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第19回は、蔦重のもとで、盟友の朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)とともに大ヒット作を世に出した恋川について解説する。
■ふざけた狂歌名を持つヒットメーカー
「酒上不埒(さけのうえふらち)」
そんなふざけた狂歌名を名乗ったことから、酒の席ではだらしない姿を見せることもあったのかもしれない。それでもやるときはやる、そんなクリエーターだったのだろう。
一度でも大ヒットを出すだけでも難しいのに、二度も自身の作品で大ムーブメントを引き起こした恋川春町(こいかわ・はるまち)のことである。
武士でありながら、絵師や戯作者、またときには狂歌師の顔を持ったこの男は、江戸時代中期に花開いた町人文化を、どのように盛り上げたのだろうか。
恋川春町は延享元(1744)年に駿河で、紀伊田辺藩士・桑島九蔵の次男として生まれた。のちに盟友となる朋誠堂喜三二より9歳年下ということになる。
宝暦13(1763)年には、駿河小島(おじま)藩に出仕。同年、20歳のときに父方の伯父で、駿河小島藩士である倉橋忠蔵の養子に入り、本名が「倉橋格(いたる)」となった。
小島藩では「中小姓」「小納戸」「取次」「側用人」「用人」「年寄」と順調に出世を果たしている。喜三二と同じく諸藩の渉外担当役である「留守居役」や、判を押す責任者「加判」などの要職を歴任していることから、マジメな仕事ぶりが上役から評価されていたのだろう。
その一方で、恋川は鳥山石燕(とりやま・せきえん)のもとで絵を学んだ。石燕は、幕府の御用絵師であった「狩野派」(かのうは)から独立。妖怪画集『画図百鬼夜行』(がずひゃっきやぎょう)を刊行し「妖怪画の祖」としても名を残している。自身で俳諧もたしなみながら、儒学者、俳人、狂歌人など幅広く交友関係を持った石燕。喜多川歌麿や栄松斎長喜(えいしょうさい・ちょうき)など、数多くの門下生が輩出されており、恋川もそんな一人となった。