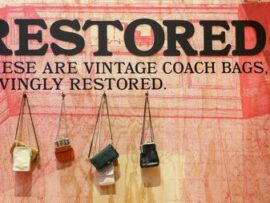■地下鉄や新幹線でスマホが通信できるワケ
仕事相手や友人とメッセージを送り合ったり、通話をしたり、さらには動画視聴、ウェブ検索など、生活の様々な場面で欠かせなくなったスマホ。そのスマホは、どのように通信しているのでしょうか。
友人と電話する際、お互いのスマホどうしが直接つながっているわけではありません。スマホが通信するとき、まずは本体から電波が飛んで「基地局」というアンテナ設備につながります。基地局は都心部や住宅地であれば、ビルやマンションの屋上に建設されています。
巨大なオフィスビルやショッピングモールなどでは、小型の基地局が屋内に設置されています。また、外からの電波が届かない地下鉄や地下街の中にも、専用のアンテナが備え付けられています。
最高速度が時速285キロメートルの東海道新幹線に乗車中も問題なく通信ができるのは、線路沿いに基地局が設置されていることに加えて、トンネルの出口から中にかけて、基地局が電波を飛ばしているからです。
次に、基地局からは光ファイバーを経由して、ネットワークセンターに音声やデータが運ばれます。ここで他社のセンターにつながるものもあれば、インターネットにつながり、YouTubeの動画やウェブ、SNSなどのサーバーとつながって、データが運ばれてくるのです。
NTTドコモ(以下、ドコモ)が「つながりにくい」と言われているのは、スマホと基地局間の問題と言われています。街中にたくさんのドコモユーザーがいて、最寄りの基地局の電波とつながる際、混雑していてデータが流れてこない状況が発生しているのです。
ドコモでは街中の基地局を増やしたり、ビルの屋上にある基地局から飛ばす電波の向きを調整したりして、多くのスマホとつながるよう、対策を講じています。
2022年7月、KDDIで大規模な通信障害が発生しました。スマホの音声通話やデータ通信が3日以上、つながりにくい状態となりました。ユーザーのスマホだけでなく、同じ電波を使うATMや物流会社のドライバーが所有する端末など、様々な機器に影響が出ています。
通信障害の原因は、データセンターで設備のメンテナンス作業を行った際に、手順を誤ってしまったこととされています。実はこのとき、実際に回線が不通になったのはたったの15分間だけです。しかし、その対処をしている間にデータが流れる道で大渋滞が発生。「輻輳(ふくそう)」という、設備での処理が追いつかない状態となり、あらゆるところに負荷がかかって障害が長引いたのでした。
我々が快適にスマホを使えるのは、端末の発する電波から基地局、光ファイバー、センターなどあらゆる場所でスムーズにデータが流れているおかげなのです。
■楽天が欲しがった「プラチナバンド」とは
日本における携帯電話のサービスは1979年、当時の日本電信電話公社(現NTT)が自動車電話としてスタートさせました。当時は「第1世代」として、アナログ方式によって音声通話を実現していました。
93年にはアナログ方式からデジタル方式となり、これが「第2世代」と呼ばれています。99年にはドコモの「iモード」が開始。音声通話だけだった携帯電話にインターネットサービスが使えるようになり、「話す」から「使う」の時代に入りました。
2000年には「第3世代」として、世界で同じ携帯電話を使えるように規格の統一が進みました。これにより、08年にアップルのiPhoneが日本に上陸します。
10年には「第4世代」となり、データ通信が強化されます。ここで一気にガラケーからスマホへの乗り換えが進みました。また、アプリによって様々なサービスが登場しました。そして、20年には最新となる「第5世代」がサービスを開始しています。
第1世代から第2世代の頃は、とにかく「全国どこでもつながること」が通信事業者に求められました。そのため、できるだけ遠くまで電波が飛ぶ基地局を設置してきました。
第1世代の電波は800メガヘルツ帯という比較的低い周波数帯で、山間部やビルの中などもカバーする設計となっていました。この周波数帯では半径数キロメートル飛ぶため、基地局も数キロメートルに1局程度の設置で済みます。このように、広い範囲をつながりやすくできる周波数帯を業界内では「プラチナバンド」と呼んでいます。
しかし、iモードが登場し、さらにスマホに進化していくと、データ通信の需要が増大していきます。その際、基地局はできるだけ数多く、密に設置していく必要があります。
3Gでは、2ギガヘルツ帯という世界中で共通的に使える周波数帯が導入されました。4Gでは6ギガヘルツ以下の周波数帯が主に使われ、5Gになると28ギガヘルツ帯の「ミリ波」という高周波数帯が導入されました。ミリ波は200メートルぐらいしか飛ばないので、スタジアムやライブ会場など、狭い場所で使われる傾向があります。
ドコモやKDDI、ソフトバンクは長年携帯電話サービスを提供していることもあり、様々な周波数帯を所有しています。また、各社は全国に20万以上の基地局を開設し、増大するデータ需要を処理しています。