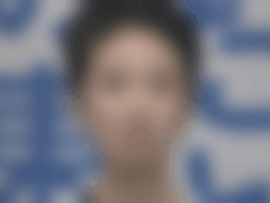戦後80年、日本がなぜ「大東亜共栄圏」へと突き進んだのかという問題について、「外務省本丸説」とも呼ぶべき、新たな視点から論じた話題書『外務官僚たちの大東亜共栄圏』(熊本史雄著、新潮選書)が刊行された。中国政治外交史の第一人者で、東京大学教授の川島真さんが同書を読み解く。
***
外務省にとっての「失敗の本質」
本書は、「大東亜共栄圏」という対外膨張策が策定された原因を、軍部の膨張主義やアジア主義、あるいは対外強硬派のイデオロギーに求めず、外務省という官僚組織、それも小村寿太郎から幣原喜重郎、そして重光葵などに至る外務省の理知的なエリート官僚たちに求め、むしろ外交思想の集大成として準備されたのがその「大東亜共栄圏」であると主張するものである。すなわち、「〈国益〉を純粋に追求すると言う外務官僚たちの思想的営為の積み重ねが、皮肉にも戦争を引き起こす結果に至った」というのである。
広く知られる、戸部良一他『失敗の本質』(中公文庫、1991年)では、日本陸軍の「失敗の本質」を陸軍の組織論に求めている。著者は、陸軍についてのその議論を認めつつ、外務省にとっての「失敗の本質」は異なるのであり、その外務省の「失敗の本質」を問うにはその前提や背景、さらには基層をなす秩序観や世界観といった観念のレベルから問い直す必要性があると述べる。外務官僚たちは「自らの権益の内在的論理からのみ発想し、他国の視座への想像力を欠いたものになったために挫折していった」のだから、その内在的理解とは何かというのが本書の出発点である。
「霞ヶ関外交」の原理とその限界
著者によれば、1934年4月13日に外務大臣の廣田弘毅から有吉明在中国公使に対して発せられた「第一〇九号電報」こそが、「ワシントン体制」に対して協調的だったそれまでの方針からの転換を表明したものであり、この電報と天羽声明などによって日本外交は後戻りできないところに至ったという。そして、それ以後事態を取り繕うために行った施策も悉く失敗に帰したという。それではこの電報が否定したのはワシントン体制だけだったのか。著者は、そうではなく、日露戦争以後の日本外交が背負い追求せねばならなかった、経済権益(とりわけ満蒙権益)の追求と対英米緊張緩和(対英米協調)という矛盾の克服に失敗したことを示しているのだという。
この矛盾はいつ形成されたのか。それは日露戦争であった。日露戦争を通じて、小村寿太郎の「満鉄中心主義」が形成され、日本の満洲(のちに満蒙)権益を諸列国に認めさせつつ、一方で「門戸開放」「機会均等」の原則を横目で睨み、両者のバランスを保つことが命題とされ、「これがのちの外務官僚たちへと継承されていくことになる」という。つまり「矛盾をはらんだ両義的な外交政策」を生み出したのは、他ならぬ小村寿太郎だったというのである。
ではなぜ外務官僚たちはその矛盾の克服に失敗したのか。著者は、外務省がこの矛盾の克服という難題に直面しながらも、結局「そもそも対英米協調があくまで経済権益の確保・拡大という命題を達成するうえで支障のない範囲ないで試みられたに過ぎなかった」という。しばしば対英米協調の旗手のように言われる幣原喜重郎でさえ、満洲事変後に撤兵の条件を自ら吊り上げた。それも満蒙権益を守るためであった。このような姿勢が「第一〇九号電報」に結びついたというのである。そして、この電報以後に陥った窮地から抜け出すための乾坤一擲の試みが大東亜共同宣言であったという。しかし、この宣言は、非現実的な地域主義であり、アジアの「解放」と資源の「開放」という両義性に揺れる、虚実の入り交じった、砂上の楼閣だったと著者は言う。矛盾の克服はもはや困難だったのである。