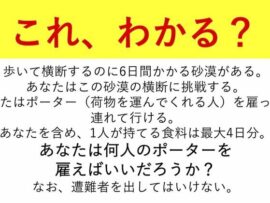入居させている家族は知らない、老人ホームの実態。60歳から介護の現場に飛び込んだ元「検診員」が見たものとは
『家族は知らない真夜中の老人ホーム――やりきれなさの現場から』(川島 徹・著、祥伝社)は、2020年8月に紹介したことがある『メーター検針員テゲテゲ日記』の著者による新刊。
あれから5年も経ったとは驚きだが、ともあれ著者はその後、10年間続けたメーター検針員の仕事を辞めさせられ、60歳から介護の仕事を始めたのだった。
その根底には「仕事の緊張感がないと生活のリズムを失ってしまいそうだ」という思いだけでなく、年金だけでは生活できないという切羽詰まった事情もあったという。
かくしてハローワークで、介護の仕事を検索するに至ったのである。
~~~
夜勤だとひと晩で1万円、高いところは1万5千円。作家になるという夢はまだ諦めてはいなかった。夜勤だと人間関係に煩わされることはないだろう。それに夜中に本が読めるかもしれない。
そんな不埒な動機で、わたしはあるグループホームの夜勤の仕事を始めた。
そこを皮切りに70歳まで10年間、8カ所あまりの老人ホームを転々とした。(「まえがき」より)
~~~
著者も認めているように、介護の現場はきつく、汚く、給与も安い。また人手不足で働き手が少ないため、介護職は引く手あまたの職業ともいえる。そのため未熟な介護者も多く、著者もそのひとりだった。
しかし過酷な状況下で、さまざまな境遇にある人々と触れ合い、よいことも悪いことも知ることになる。
「怖いっ。男が注射をするの、とても痛いの」
熊本市で歯科医を開業していたものの、脳梗塞で左半身麻痺となり、奥さんとも離婚した井上秀夫さん。
糖尿病を患っており、背中や腕にイレズミをしている(が、じつはやさしい気遣いができる)彫物師の上村辰夫さん。
ヘビースモーカーで面倒見のいい一杯飲み屋の元女将、伊藤ミネさん。
48歳ながら足腰が弱り、介助なしには立てなかった刑務所帰りの竹下ミヨ子さん。
この人々はほんの一例にすぎないが、患者さんは濃いキャラクターの持ち主ばかりである(登場人物はすべて仮名)。
~~~
「恐いです。行かないでください」
前田さんは掛け布団を顎まで引き、小さな手でその縁を掴んでいた。
「何が恐いの。みんな居るのよ。何も恐いことなんかないのよ」
介護者としての職業的な笑顔とやさしさで慰めた。
「男たちが、居るんです。窓の外に男たちが居て石を投げるのです」
「そ、そんなことはないよ。誰も居ないよ。安心して」
「ほらほら、石を投げるの。4、5人居る。恐いの」
しだいに話は切迫感を帯びてきた。
「恐いっ。そこに居てください。男が注射をするの、大きな注射をお尻にするの、とても痛いの、そこに居てください。この時間になるといつも出てくるんです。誰も助けてくれないの、いつもがまんしているんです、そこに居てください、ひとりにしないでください」(35〜36ページより)
~~~
こう主張する前田さんは小柄で穏やかな性格の女性だが、幻視が現れるレビー小体型認知症なのだという。確かに介護者からすれば、対応に悩まされることだろう。幻視であるとはいえ、注射器を持った男たちが見えている本人にとって、それは「真実」だからだ。