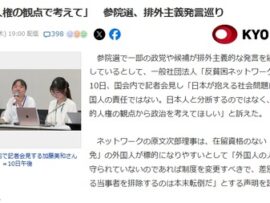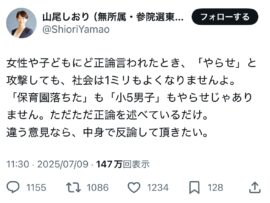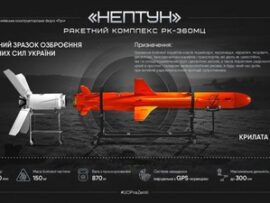警察庁は、改正道路交通法の運用に基づき、自転車の交通違反に対する反則金制度、いわゆる「青切符」における反則金額を公表しました。この新しい制度の下では、自転車の違反行為に対し、以下のような反則金が通告されます。二人乗りは3000円、信号無視は6000円、指定場所一時不停止も6000円、安全運転義務違反(逆走や歩道での危険な通行など)も6000円となります。特に携帯電話を使用しながらの運転(ながら運転)は1万2000円と、比較的高い金額設定となっています。この発表に対し、パブリックコメントでは意見が大きく分かれ、「高すぎる」という声と「安すぎて抑止力にならない」という声がほぼ同数寄せられたといいます。これは、主に自転車利用者と、自転車を利用しない歩行者との間で視点が異なっているためと考えられます。
 自転車の交通違反を取り締まる警察官の様子
自転車の交通違反を取り締まる警察官の様子
自転車「青切符」の具体的な反則金額
今回の警察庁による公表で明らかになった主な自転車交通違反の反則金額は以下の通りです。
- 二人乗り: 3000円
- 信号無視: 6000円
- 指定場所一時不停止: 6000円
- 通行禁止違反 (逆走など): 6000円
- 歩道通行時の義務違反: 6000円
- 安全運転義務違反(ながら運転など、携帯電話使用含む): 1万2000円
これらの金額は、これまでの警告や講習とは異なり、金銭的な負担を伴うものとして、自転車利用者にとって重要な変更となります。
パブリックコメントに見る意見の対立
今回の反則金設定に対するパブリックコメントでは、その金額の妥当性を巡って意見が二分されました。一部からは「家計に大きな負担となる」「自転車は車と違う」として金額が高すぎるとの指摘がありました。その一方で、「これまでの罰則が軽すぎた」「事故防止のためにはもっと高くすべきだ」「抑止効果が期待できない」といった、金額が安すぎるとする意見も同程度寄せられています。この意見の衝突は、自転車を日常的に利用する人々と、主に歩行者として自転車と接触する機会が多い人々との間で、安全や交通ルールに対する優先順位や認識が異なることが背景にあると考えられます。
なぜ今、決定プロセスに疑問の声があがるのか
今回の自転車反則金制度に限らず、近年、法律や制度が可決・成立した後に、その運用段階になって初めて国民の間で大きな混乱や賛否両論が巻き起こるケースが散見されます。後期高齢者の医療費負担増やマイナンバー制度などがその例として挙げられます。日本は民主主義国家であり、主権者たる国民が選んだ代表者で構成される国会こそが、法律を議論し制定する場であるべきです。
特に、今回の自転車に関する問題のように、自転車利用者と歩行者といった異なる立場の間で利害が真っ向から対立するような事例では、法案が可決される前にこそ、多角的な意見が国会で徹底的に議論され、合意形成が図られるべきです。各政党や個々の議員は、自身の支持基盤に自転車利用者側と歩行者側の双方が含まれるため、本音ではどちらの票も失いたくないという思いから、法案審議中は詳細な議論を避け、党議拘束に従って形式的に賛成したのではないかという批判も上がっています。しかし、このように国民生活に直結する実務的な問題で、有権者の懸念や困惑を十分に解消しないまま決定を進める姿勢は、民主主義の健全な機能にとって看過できない問題と言えるでしょう。イデオロギー的な対立には熱心に議論する一方で、こうした具体的な生活課題に対する議論が不十分である現状は、改善される必要があります。
施行を前に問われる民主的な議論のあり方
自転車への「青切符」導入は、長年の課題であった自転車の危険運転に対する対策として一定の評価ができる側面がある一方で、その具体的な制度設計や金額設定、そして最も重要な決定に至るまでのプロセスにおいて、国民の間に疑問や不信感を生じさせています。今回の件は、立法府が国民の多様な意見を十分に聞き、利害の対立を調整するための議論を尽くすことの重要性を改めて浮き彫りにしました。新制度の施行を前に、なぜこのような形で議論が再燃しているのかを深く理解し、今後の政策決定プロセスに活かすことが、健全な民主主義を維持するために不可欠と言えるでしょう。