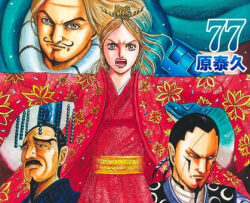日本を牽引するリーダー育成を目指し、トヨタ自動車など大手企業3社が設立母体となった海陽学園。その最大の特徴である全寮制教育について、同学園の西村英明校長と中学受験PREX代表の渋田隆之氏が対談した。学力偏重ではない、社会で生きる力を育む海陽学園の独自の取り組みに迫る。
企業が抱いた危機感が生んだ全寮制教育
海陽学園が全寮制を採用する背景には、学校教育だけでは将来の日本を担うリーダーを育成しきれないという設立母体企業の危機感があった。トヨタ自動車、東海旅客鉄道(JR東海)、中部電力の3社は、家庭や地域社会も含めた教育の場が必要だと考え、通学を一切認めない全寮制を選んだ。これは、学力だけでなく、社会で活躍するために不可欠な力を育むための必然だったと言える。
学校教員とは異なる独自の寮運営スタッフ
海陽学園の寮制度が他の学校と大きく異なる点の一つは、寮の運営を学校教員とは別の専門スタッフが行っていることだ。生徒60人に対し1人の割合で「ハウスマスター」と呼ばれるお父さん役、そして20人に対し1人の割合で企業から派遣された若手社員が「フロアマスター」としてお兄さん役を務める。彼らは教員ではないからこそ、学習指導ではなく、共同生活を通じて生徒が社会で求められる力を身につけるための支援に注力している。西村校長自身も初代ハウスマスターの経験を持つ。
授業だけでは学べない「非認知能力」を育む寮生活
寮生活は、学校の授業で学ぶ学力とは異なる、いわゆる非認知能力を育む重要な場として位置づけられている。学校での学習における問題解決には明確な正解があることが多いが、寮での共同生活で直面する問題には唯一の答えがない。例えば、60人に対して洗濯機が8台しかない状況で、どうすれば全員がスムーズに洗濯を終えられるかを考えるには、単なる知識ではなく、状況判断、交渉、協力といった問題解決能力が求められる。メンバー構成や状況によって最適な運用は変わり、試行錯誤や失敗を繰り返しながら最適な方法を見つけ出していく過程そのものが学びとなる。
また、集団生活の中では、苦手な人や意見の合わない相手とも向き合わなければならない。そうした人間関係の構築や調整も、寮生活を通して自然と身についていく。このように、海陽学園の全寮制教育は、教室での学びを補完し、社会に出てから本当に必要となる実践的な力を養うことを目的としている。
 海陽学園のハウスイベントで行われた夏祭りにて、寮生たちがすいか割りを体験し、集団生活の中での楽しみを共有している様子
海陽学園のハウスイベントで行われた夏祭りにて、寮生たちがすいか割りを体験し、集団生活の中での楽しみを共有している様子
結論として、海陽学園の全寮制は単に生徒を預かる場所ではなく、企業が日本の未来を憂い、学力のみならず社会で生き抜くための非認知能力や実践的な問題解決能力、豊かな人間関係構築力を育むために設計された独自の教育システムの中核をなしている。ハウスマスターやフロアマスターといった独自のサポート体制の下、生徒たちは集団生活の様々な局面を通じて、将来リーダーとして社会に貢献するための土台を築いていると言えるだろう。
本記事は、Yahoo!ニュースに掲載されたダイヤモンド・オンラインの記事を基に構成されています。