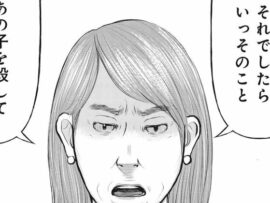沖縄で深刻化する「子供の貧困」。本土で報じられる給食費や授業料の未払いに比べ、沖縄の貧困はより複雑で根深い問題を抱えていると指摘するのは、沖縄県の児童相談所などで長年福祉に携わってきた専門家、おきなわ子ども未来ネットワーク代表理事の山内優子氏だ。山内氏は、自身が目にしてきた沖縄の厳しい現状に「率直に驚いた」とその異質性を語る。
沖縄特有の「負の連鎖」とその歴史的背景
沖縄県の離婚率は全国で最も高く、それに伴うひとり親世帯の貧困率も63.3%(2021年)と極めて高い。日中、育児に時間を取られる母親は、生活費を稼ぐため夜間に働くケースが多い。親が不在がちな思春期の子どもたちは、寂しさから夜の街を彷徨い歩くようになり、一部の若い女性が望まない妊娠に至るという「負の連鎖」が見られる。これは、まさに「子による子育て」とも言える過酷な状況だ。
 経済的困難を抱える若年ママと子どもたち
経済的困難を抱える若年ママと子どもたち
この構造には、沖縄特有の歴史が深く関わっていると山内氏は指摘する。本土では1947年に児童福祉法が制定され、母子寮や保育所などの整備が進められたが、アメリカ統治下にあった沖縄には日本の法律が適用されず、本土復帰の1972年時点で母子寮や児童館は一つも存在しなかった。戦後から復帰までの「空白の27年間」における福祉基盤整備の遅れが、現代の子供たちにも影を落としている。
未来を拓くための多様な支援
こうした状況に対し、山内氏は対症療法的な支援だけでは限界があると感じ、貧困の再生産を断ち切り、母子共に安心して暮らせる社会を目指して2018年におきなわ子ども未来ネットワークを設立した。19年からは妊娠発覚時の相談事業を開始し、高額な中絶費用の代替として21年には避妊リングの無料提供制度を導入。住む場所がない妊産婦のための宿泊型居場所も整備するなど、多角的な支援を展開している。
活動を続ける中で山内氏が痛感したのは、若年ママにとって自動車運転免許がいかに重要かということだ。公共交通機関が限られる沖縄では、免許がなければ仕事探しや通勤、病院への通院、日々の買い物すら困難を極める。しかし、経済的に困窮している若年ママには免許取得の費用を捻出する余裕がない。「炎天下、毎日1時間かけて子供を保育園へ歩いて送迎する母親もいた。何とかしなければと思った」と山内氏は語る。
免許取得支援プログラム:自立への確かな一歩
「働きたい」と強く願う若年ママたちの自立を後押しするため、山内氏らは県の予算を活用し、運転免許取得費用を全額助成する事業を2022年に開始した。初回募集では、わずか6人の定員に対し、実に80人もの応募があったという事実は、この支援がいかに切実に求められていたかを物語っている。自動車免許は、沖縄で暮らす多くの若年ママにとって、経済的自立、ひいては貧困の連鎖を断ち切るための不可欠なツールとなっている。
結び
沖縄における子供の貧困問題は、本土とは異なる歴史的背景や社会構造が絡み合った複雑な課題である。特に若年ママとその子供たちが直面する困難は深く、その「負の連鎖」を断ち切るためには、妊娠期からの相談支援、居場所の提供、そして地域特性に応じた免許取得支援のような、具体的な自立に向けたサポートが極めて重要となる。おきなわ子ども未来ネットワークのような草の根の活動は、厳しい環境に置かれた母子の未来を切り拓くための希望となっている。
[Source link] (https://news.yahoo.co.jp/articles/4cc2f3b244663b4a480ff578037a9cc92b0156a4)