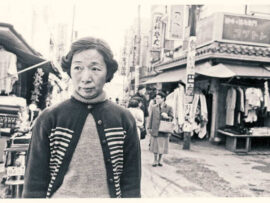近年、都市部における分譲マンション価格の高騰が注目される一方で、築年数が経過し老朽化したマンションの維持管理は深刻な課題となっています。区分所有法の改正案が今国会で可決・成立したことは、こうした問題への対応が急務であることを示唆しています。ノンフィクションライターの栗田シメイ氏は、長年にわたり、独裁的な理事会による「謎ルール」によって資産価値が著しく下落した「秀和幡ヶ谷レジデンス」を取材してきました。この事例は、集合住宅に住む誰もが直面しうる「自治」の難しさを浮き彫りにします。
老いるマンションの増加と法改正の動き
築年数を重ねたマンションが増加するにつれて、住民間のトラブルが顕在化し、マンション管理のあり方を問う声が高まっています。約60年ぶりの大幅な改正となる区分所有法を中心としたマンション関連法改正案の成立は、まさに時代の要請と言えるでしょう。筆者が出版した『ルポ秀和幡ヶ谷レジデンス』(毎日新聞出版)は、30年近くにわたり理事会が独裁的な運営を行い、奇妙なルールが次々と生み出されたマンションの顛末を描いています。その異常な管理体制から、一部では「渋谷の北朝鮮」と揶揄された秀和幡ヶ谷レジデンスは、年を追うごとに資産価値が低下しました。
極端な管理体制が招いた資産価値の下落
秀和幡ヶ谷レジデンスの資産価値は、最も低い時期には現在の半分以下、1500万円台まで下落したことがあります。不動産業者は、「相場の3割、4割に設定しても、旧理事会の悪評を理由に売れなかった」と証言しています。しかし、理事会が交代した後は、資産価値が急激に回復し、売買も活性化しています。この事実は、マンションの管理体制が資産価値に極めて大きな影響を与えることを明確に示しています。
 秀和幡ヶ谷レジデンスの外観。管理体制の問題が取り沙汰されたマンション。
秀和幡ヶ谷レジデンスの外観。管理体制の問題が取り沙汰されたマンション。
驚くべき「謎ルール」の数々
旧理事会が展開した管理体制下で課せられたとされるルールには、以下のような驚くべきものがありました。
- 家族や友人を連泊させる場合、「転入出金」として1万円の支払いが求められる。
- 専有部分であっても、1ヵ月を超える工期のリフォームは禁止。
- 介護ヘルパーやベビーシッター、工事関係者などの入館は、平日17時以降と日曜日・祝日は禁止。
- ウーバーイーツなどのデリバリーサービスの利用禁止。
- 廊下での立ち話や携帯電話での通話禁止。
- 購入した部屋を賃貸に出す際、外国人や高齢者には貸し出してはならない、といった不合理な条件を管理組合から突きつけられる。
- マンション購入時にも管理組合による面接がある。
さらに取材で集まった証言からは、「引っ越しの際に管理人に荷物チェックをされた」「パソコンは一世帯一台までと決められ、仕事道具の持ち込みが著しく制限された」「オーナーに無断で工事が行われ、業者から高額請求が届いた」といった、住民の生活や権利を著しく侵害するような事例も明らかになっています。
8人の住民が立ち上がった「政権奪還」の闘い
こうした圧政とも言える状況に対し、わずか8名の住民が立ち上がり、長年の独裁体制を終わらせ、管理組合の「政権」を取り戻すまでの闘いが『ルポ秀和幡ヶ谷レジデンス』では描かれています。この奇跡的な物語は、困難な状況下でも住民が協力し、自らの居住環境を守り、改善していくことの重要性を教えてくれます。
結論:マンション自治の現実と未来
秀和幡ヶ谷レジデンスの事例は、一部の管理組合が抱える深刻な問題が、住民の日常生活の質だけでなく、マンションという資産の価値にも壊滅的な影響を与えうることを明確に示しました。今回の区分所有法改正は、こうした極端な事例を含む、老朽化マンションが抱える多様な課題に対処するための重要な一歩です。集合住宅における「自治」は、住民一人ひとりの無関心や、一部の独断専行によって容易に機能不全に陥る脆い側面を持っています。しかし、この事例が示すように、住民が主体的に関与し、問題を解決しようと行動することで、状況は劇的に改善される可能性があります。日本の多くのマンションが今後老朽化を迎える中で、秀和幡ヶ谷レジデンスの教訓は、マンション管理のあり方、そして住民の役割について、私たちに深く考えさせる示唆を与えています。
[Source link ](https://news.yahoo.co.jp/articles/8dcaeb032092f7a5e4994ee123634ae88dff0f20)