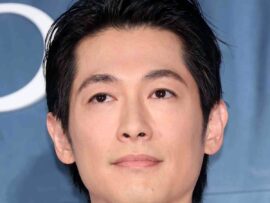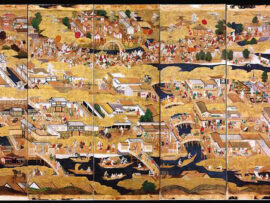太平洋戦争の戦局悪化に伴い、旧日本軍の兵士たちは「玉砕」という悲劇的な最期を遂げることが相次いだ。なぜこのような事態が起きたのか。本稿では、当時の日本陸軍の指導部にいた軍人たちの特徴を探ることで、その背景にある構造的な問題と、悲劇が繰り返された理由に迫る。彼らの教育、経験、思想には、組織の崩壊を予見させる致命的な欠陥が存在していた。
指導者世代の背景と教育
太平洋戦争を指揮した陸軍の指導層は、主に明治10年代後半から20年代にかけて生まれた世代である。彼らに共通するのは、陸軍幼年学校、陸軍士官学校、そして陸軍大学校(陸大)といったエリート教育機関を優秀な成績で卒業している点だ。これらの学校は成績至上主義の傾向が強く、彼らはそのシステムの中で優れた評価を得て昇進してきた。
しかし、この世代の多くは実戦経験に乏しかった。例えば、明治37、38年(1904、05年)の日露戦争の際には、まだ陸軍士官学校や陸軍幼年学校の生徒に過ぎず、中隊長として部分的に参戦した者はいても、大規模な実戦を指揮する立場ではなかった。この経験の欠如は、後の戦局判断や戦略立案に影響を与えた可能性が高い。
 1943年、陸軍将校らが東條英機に敬礼する様子。昭和陸軍指導部の雰囲気を伝える一枚。
1943年、陸軍将校らが東條英機に敬礼する様子。昭和陸軍指導部の雰囲気を伝える一枚。
陸軍の伝統と外部からの影響
この世代の軍人は、近代日本の富国強兵政策が生み出した軍人養成システムと精神的規範の産物とも言える。与えられた枠組みの中で考え、行動することには長けていたが、独創的な識見や歴史的先見性を持つという点では限界があった。
ただし、彼らが果たした重要な役割の一つに、日本陸軍内部を長年支配していた長州閥の打破が挙げられる。元勲である山県有朋が死去するまで、陸軍の主導権は長州出身者が握っており、「長州の三奸」と揶揄されるような軍人も存在した。この旧弊な閥族支配を彼らの力によって終焉させたことは、組織の刷新という面で評価できるかもしれない。
また、太平洋戦争を担った軍事指導者には、「親ドイツ、反英米」という考えが強く根ざしていた。元々、日本陸軍はフランス陸軍を模範として建軍されたが、普仏戦争でのフランス敗退後、ドイツ陸軍を模倣するようになった。明治10年代にはドイツ軍人が日本に招かれ、陸大でドイツ式の軍事教育や精神教育が行われた。陸軍幼年学校でもドイツ語やロシア語が中心で、英語教育は軽視された。これは、親英米感情を持つ者を少なくし、結果的に一般中学出身者が要職から外される要因ともなった。
「人間」軽視の思想とその表れ
さらに、昭和陸軍の軍事指導者には、〈人間〉に対する洞察力が著しく欠けていたという点が指摘される。彼らは哲学的、倫理的な側面から人間を捉えることができず、単に戦時消耗品と見なす傾向から抜け出せなかった。
この思想は、具体的な作戦や方針に如実に表れた。例えば、つねに歩兵による肉弾攻撃を重視したこと、兵士を無機質な兵器のように扱うことに固執したこと、そして補給や兵站思想を軽んじたことなどが挙げられる。意味もなく兵士たちに玉砕を命じながら、それに対して反省することなく同様の作戦を繰り返したことも、この人間軽視の表れであった。
結論
太平洋戦争という昭和陸軍崩壊の主因となった戦いは、成績優秀だが実戦経験に乏しく、特定の外国思想に偏り、そして人間を軽視する傾向があった指導者たちによって遂行された。彼らの体質、戦略、そして戦争観には、組織が崩壊するのが当然と言えるような根本的な問題が宿っていたと言えるだろう。太平洋戦争の期間中、首相、陸相、参謀総長などを兼任して戦時指導にあたった東條英機は、まさにこのような指導者層の特徴を最もよく代表していた人物の一人である。その前任者である杉山元参謀総長も、日露戦争での下級将校としての経験はあったものの、概ねこの共通する枠内に収まる軍人であった。これらの指導者たちの特性が、数多の悲劇、特に「玉砕」という無謀な犠牲を強いる戦いを繰り返し引き起こした主要因であったと言えるだろう。
出典:保阪正康著『昭和陸軍の研究 上』(朝日文庫)