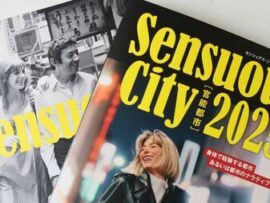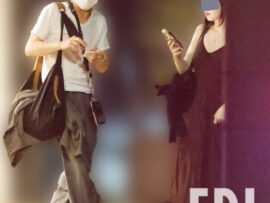賃貸物件において入居者が死亡した場合、その部屋は一般的に「事故物件」と呼ばれ、新たな借り手を見つけることが著しく困難となるケースが多く見られます。この状況は貸し手であるオーナーにとって、原状回復費用に加え、家賃の大幅な減額や空室期間の長期化といった経済的な損失をもたらし、対応に苦慮する要因となります。
東京都心部に所在するタワーマンションの一室を所有するオーナーが直面した事例では、その物件の借主の一人がバルコニー(13階)から転落し死亡するという事故が発生しました。これにより物件は「自殺のあった物件」として扱われ、新規の賃借人が見つかりにくくなった上、従前の月額賃料23万5,000円から15万円への減額を余儀なくされました。オーナーは、この事故物件化による損害、具体的には家賃減額分と空室期間の賃料相当額として合計564万円(賃料の24ヵ月分に相当)の賠償を求め、亡くなった借主と同居していたもう一人の賃借人および亡くなった借主の相続人らを相手取り提訴しました。
一方、訴えられた賃借人側は、亡くなった借主の死因は自殺ではなく転落事故であったこと、また事故が発生したのが貸室内ではなくバルコニーであったことから、損害賠償責任は負わないと主張し、オーナーの請求を争いました。
 東京都心の賃貸タワーマンション外観イメージ
東京都心の賃貸タワーマンション外観イメージ
本件訴訟は、東京地方裁判所における令和4年10月14日判決で取り上げられた事例を基にしたもので、賃貸物件で発生した死亡事故に伴う「心理的瑕疵」(物件に心理的な抵抗感を与える欠陥)に関する重要な裁判例の一つです。この裁判では、主に以下の3つの点が主要な争点として審理されました。
争点1:賃借人の死因は自殺か否か
本件では、監察医による死体検案書やバルコニーの構造といった状況証拠から、飛び降りによる死亡である可能性が強く推測されました。しかし、賃借人側は事故死の可能性を主張したため、亡くなった賃借人の正確な死因が法的にどのように認定されるかが最初の大きな争点となりました。死因が自殺か事故かによって、その後の責任の所在や損害賠償の範囲に影響を及ぼす可能性があるためです。
争点2:賃借人に「自殺をしない義務」は含まれるか
賃貸借契約において、賃借人には通常、「善良なる管理者の注意をもって目的物を使用収益する義務」(善管注意義務)があるとされています。この善管注意義務の中に、「賃貸物件内で自殺しないこと」という義務が含まれるのかどうかが問題となりました。さらに、賃借人が物件内で自殺することが、当該物件に心理的瑕疵を生じさせ、オーナーに損害を与えることを予見できたかどうかも、この争点において重要な考慮事項となりました。賃借人が予見可能性を持っていたか否かが、責任の有無や範囲を判断する上で影響を与える可能性があります。
争点3:賃借人の自殺と賃貸人の損害との相当因果関係
賃借人の死亡(本件では転落死)によって物件が事故物件となり生じたオーナーの損害(家賃減額、空室期間の賃料損失など)と、その死亡との間に法的な「相当因果関係」が認められるか、認められるとしてその範囲、期間、金額はどの程度かが詳細に検討されました。特に、物件が東京都心部のタワーマンションという特性を持つことや、死亡場所が貸室内ではなくバルコニーであったという特殊な事情が、生じた損害の評価(金額や期間)にどのように影響するかが重要な論点となりました。死亡場所の違いが、物件の心理的瑕疵の程度に違いをもたらすかどうかが問われました。
これらの争点は、賃貸物件における予期せぬ死亡事故が発生した場合に、オーナーが被る損害について誰がどこまで責任を負うべきかを判断する上での法的・実務的な課題を浮き彫りにしています。裁判所の判断は、今後の同種の事例における重要な指針となります。
出典:東京地方裁判所令和4年10月14日判決事例(弁護士 北村亮典氏解説)