「月収が上がったのに、手取りはほんの少ししか増えていない…」そんな経験をしたことのある方は多いでしょう。例えば、月収が25万円から28万円に増えたとしても、手取りの増加分は期待したほどではないと感じるかもしれません。これは間違いや計算ミスではなく、日本の給与システムにおける控除の仕組みに理由があります。昇給しても手取りがわずかしか増えない背景と、その仕組み、そして対策について詳しく解説します。
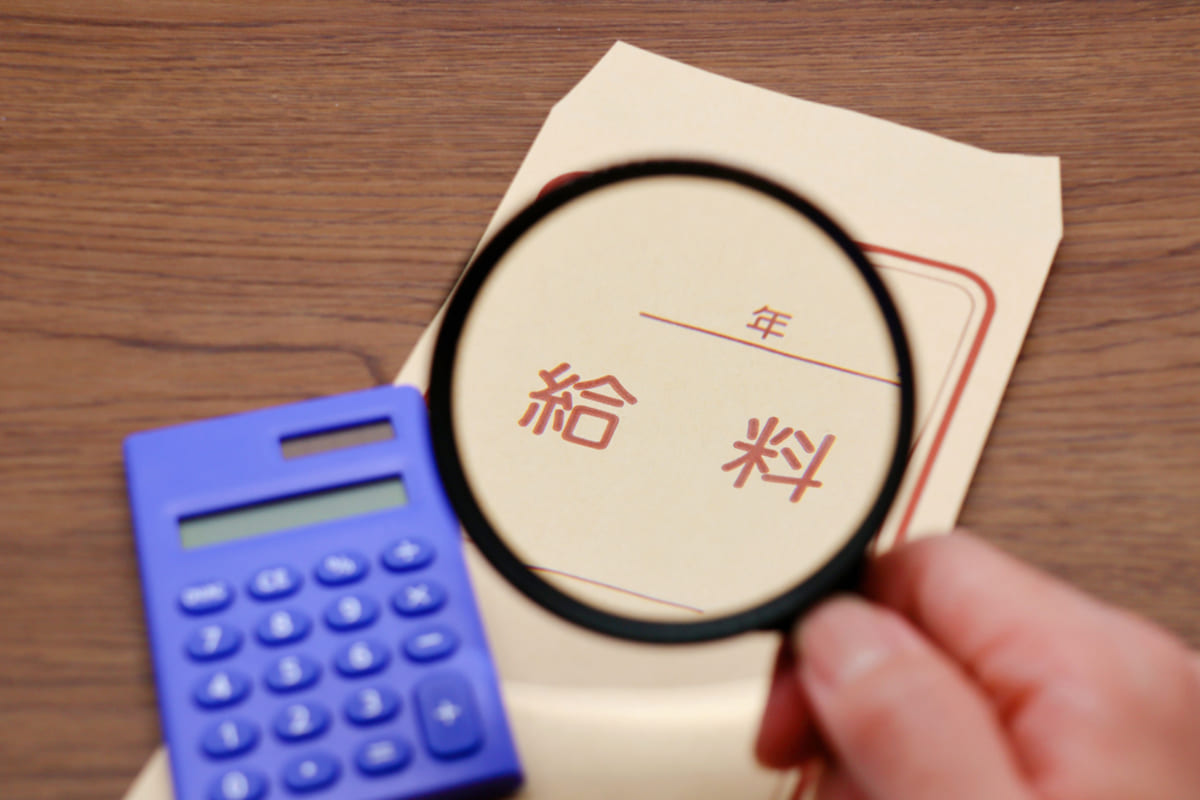 給与明細を見ながら、昇給による手取り額の変化を確認する様子のイメージ
給与明細を見ながら、昇給による手取り額の変化を確認する様子のイメージ
昇給しても手取りが増えない仕組みとは
月収が3万円増えれば、そのまま手取りも3万円増えると考えがちですが、現実は異なります。昇給によって総支給額が増えると、それに伴って「税金」と「社会保険料」の控除額も増加するからです。特に、日本の税金制度は所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が採用されており、社会保険料も原則として所得に応じて計算されます。そのため、昇給分の多くがこれらの控除によって相殺され、手元に残る手取り額の増加が限定的になってしまうのです。「昇給したのに手取りがほとんど変わらない」と感じるのは、この控除の仕組みを理解していない場合に生じる疑問です。
給与明細で引かれている「控除」の具体的な内訳
給与から差し引かれる「控除」項目は、主に社会保険料と税金です。これらがどのように計算され、昇給によってなぜ増えるのかを見ていきましょう。
社会保険料
社会保険料は、将来の安心や万が一の事態に備えるための重要な費用です。原則として、標準報酬月額(毎月の給与などを区切りの良い額で区分したもの)に基づいて保険料が決まります。昇給により月収が上がると、この標準報酬月額が上がり、社会保険料も増加します。
- 健康保険料: 病気やけがの際の医療費、出産育児一時金などの給付に使われます。
- 厚生年金保険料: 老後の年金、障害年金、遺族年金などの原資となります。将来受け取る年金額に影響します。
- 雇用保険料: 失業時の基本手当や、育児休業給付金、介護休業給付金などに充てられます。
- 介護保険料: 40歳になると負担が発生します。介護が必要になった際にサービスを利用するための保険料です。
税金
所得税と住民税は、所得に対して課される税金です。昇給により所得が増えれば、税負担も増加します。
- 所得税: 1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。日本の所得税は累進課税制度のため、所得が増えるほど税率が段階的に高くなります。給与からは源泉徴収として概算額が天引きされ、年末調整で精算されます。
- 住民税: 前年の所得に基づいて計算され、翌年の6月から1年間かけて徴収されます。昇給があった年の住民税は翌年度に影響するため、昇給した翌年度に手取りがさらに減ったように感じることもあります。
これらの社会保険料と税金が、昇給によって増えた月収から差し引かれるため、手取り額の伸びが鈍くなるのです。
手取り額を実質的に増やすための対策
昇給による手取りの増加が少なくても、賢く対策することで実質的な手取りや家計のゆとりを増やすことが可能です。
1. 所得控除や税額控除を最大限に活用する
税金の負担を軽減するための制度を利用しましょう。所得控除は所得から差し引かれ、税額控除は税額自体から差し引かれることで、課税される所得や税金が減り、結果的に手取りが増えます。
- 医療費控除: 1年間で一定額以上の医療費を支払った場合に適用できます。
- ふるさと納税: 応援したい自治体に寄付をすることで、寄付金額の一部が所得税や住民税から控除・還付されます。返礼品を受け取れるメリットもあります。
- 生命保険料控除、地震保険料控除: 加入している保険の種類に応じて控除が受けられます。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISA: これらは資産形成の制度ですが、掛け金や運用益に税制優遇があり、所得税や住民税の負担を軽減する効果も期待できます。
2. 会社の福利厚生制度をフル活用する
会社が提供する福利厚生の中には、利用しても所得として課税されない「非課税」のものがあります。これらを上手に利用することで、実質的な手取りが増えたのと同じ効果が得られます。通勤手当(非課税限度額あり)や、一定条件を満たす食事補助などがこれにあたります。ただし、住宅手当のように課税対象となる福利厚生もあるため、会社の制度や税法上の扱いを確認することが重要です。
3. 無理のない範囲で副収入や資産運用を検討する
本業の給与だけでなく、副業による収入を得たり、資産運用で資産を増やしたりすることも手取り(または総資産)を増やす方法の一つです。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されていないか、または副業の種類に制限がないかなどを事前に確認しましょう。資産運用はリスクを伴うため、無理のない範囲で計画的に行うことが大切です。
まとめ:昇給の恩恵を正しく理解し、お金と賢く付き合う
昇給しても手取りが思ったほど増えないのは、社会保険料や税金が増えるためであり、決して「損をしている」わけではありません。日本の社会保障や税制を支えるための必要な負担です。しかし、この仕組みを理解し、自分にできる対策を講じることで、昇給の恩恵を最大限に受けることや、実質的な手取りを増やすことが可能です。
給与明細を定期的に確認し、控除の内容や金額の変動に関心を持つことから始めましょう。そして、税制上の優遇措置や会社の福利厚生制度を積極的に活用してください。こうした知識を身につけ、賢くお金と向き合う姿勢を持つことが、将来の経済的な安定につながります。
参照元: FINANCIAL FIELD編集部






