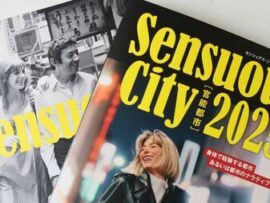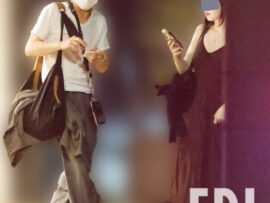内閣府の推計によると、令和47年(2065年)には日本人の平均寿命は男性84.95歳、女性91.35歳に達すると見込まれています。この超高齢社会化と少子化による人口減少は、日本の未来に想像以上の影響を与える可能性があります。長らく指摘されてきた日本の少子高齢化は、私たちの社会構造を根本から変えつつあります。
2060年、高齢者割合はどうなる?データが示す未来
日本の総人口は、2008年に過去最多を記録した後、減少局面に入りました。この人口減少、特に少子化の背景には、内閣府が要因として挙げる「非婚化」「晩婚化」「晩産化」があります。1970年代後半からの20歳代女性の未婚率上昇、結婚年齢の上昇、そして30歳代以上の女性の未婚率上昇が、未婚化と晩婚化を同時に進行させてきました。
この傾向が続けば、2050年には日本の総人口は1億人を下回ると予測されています。さらに、2060年には「約2.5人に1人」が高齢者となる見込みです。地域別に見ると、例えば東京都の人口も2025年の1,398万人をピークに減少に転じ、2060年には1,173万人になると予想されています(東京都政策企画局調べ)。これらのデータは、高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少が同時に進む、前例のない社会構造の変化を示唆しています。
 日本の将来の高齢化率や人口減少の傾向を示すイメージ
日本の将来の高齢化率や人口減少の傾向を示すイメージ
団塊ジュニア世代が直面する現実とその影響
今後の日本社会を考える上で重要な存在となるのが「団塊ジュニア世代」です。これは、第2次ベビーブーム世代(おおよそ1971年〜74年生まれ)を指し、現在50歳〜54歳を迎えています。彼らはバブル崩壊後の「就職氷河期」を経験し、その後の長引く不況下でキャリアを築いてきました。「競争社会」の象徴とも言えるこの世代は、高度経済成長期を知る親世代との間に生活感覚のギャップを感じることも少なくありませんでした。彼らが今後高齢期を迎えることで、社会保障制度や労働市場にさらなる影響が及ぶと考えられます。
まとめ:避けられない社会構造の変化
日本の少子高齢化と人口減少は、もはや避けられない現実として、平均寿命の延伸と共に進行しています。2060年には国民の約4割が高齢者となるという推計は、社会全体でこの変化にどう適応していくかという、喫緊の課題を突きつけています。団塊ジュニア世代が高齢期に入る「2040年問題」など、世代ごとの課題も複雑に絡み合っており、これらの統計データは、日本の未来図を描く上で重要な出発点となります。
参照元
- 内閣府HP: https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf (人口・経済・地域社会をめぐる現状と課題より抜粋)
- 東京都政策企画局HP: https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/jinko-mirai/jinko-suikei/ (将来人口推計より抜粋)
- 記事原文: Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/0a8f92813862456b36217aa656909b8fe64c1b24)