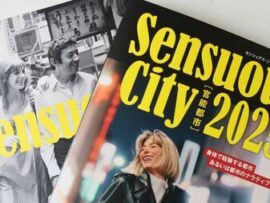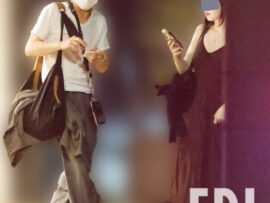日本の「国民負担率46%」という数値を聞いて、「働いても給料の半分近くが税金や社会保険料で取られるのか?」と不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、この「国民負担率」が意味するところと、実際の給与から差し引かれる金額は必ずしも同じではありません。本記事では、この数字の本当の意味を分かりやすく解説します。
 国民負担率46%を説明する図解イメージ:所得から差し引かれる税金と社会保険料
国民負担率46%を説明する図解イメージ:所得から差し引かれる税金と社会保険料
国民負担率とは:税金と社会保険料の合計
国民負担率とは、国民全体の所得(国民所得)に対する税金と社会保険料(年金、健康保険、介護保険など)の合計額の割合を示す指標です。財務省の公表によると、令和7年度の日本の国民負担率は46.2%が見込まれています。これは、国民が得た所得のうち、約半分がこれらの公的負担に充てられることを示唆していますが、この数値はあくまで「平均値」であり、個々の所得水準によって負担率は異なります。
手取りが半分になるわけではない理由
「国民負担率46%」という数字を聞いて、「手取りが半分になる」と直感的に考えるのは正確ではありません。実際に毎月の給与明細から控除される所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料などの合計額は、年収や扶養家族の有無にもよりますが、概ね15%から25%程度に収まることが多いです。国民負担率には、企業が負担する社会保険料分や、私たちが普段の買い物で支払う消費税などの「間接税」も含まれています。そのため、国民負担率は個人の給与明細で直接実感する負担額よりも高い数値となるのです。
国際比較:日本は中間レベル
日本の国民負担率46.2%を国際的に比較するとどうでしょうか。財務省のデータによれば、OECD加盟国の中にはフランスやスウェーデンなど50%を超える国がある一方で、アメリカやスイスは日本より低い水準にあります。日本は主要先進国の中では中間的な位置づけであり、「特別に高い」というわけではありません。
高齢化による将来的な負担増とまとめ
今後、高齢化が一層進むことが予測されており、これに伴い社会保険料の負担が増加する見通しです。そのため、国民負担率は今後も上昇傾向が続くと考えられています。
今回の内容をまとめると、日本の「国民負担率46%」は国民所得全体に対する税金と社会保険料の割合であり、個人の給与から直接差し引かれる手取り額が半分になるという意味ではありません。しかし、国際比較では中間レベルとはいえ、少子高齢化の影響で将来的な負担増が見込まれる点には注意が必要です。
参考資料:Yahoo!ニュース掲載記事