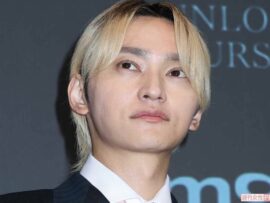「寮のある学校」は国内外で増えている
「学生寮」というと遠方に住む生徒の生活拠点で、先輩との上下関係や規則が厳しく、施設としても決して魅力的とはいえない環境を想像する人が多いのではないだろうか。だが、現代の寮は明るく清潔で快適な施設が多くなっている。イギリスのボーディングスクール日本校や私立にとどまらず、公立や高専などでも寮を設ける学校が出てきている。その背景には、社会と学び方の大きな変化があるようだ。
【表と写真で見る】寮のある主な学校。現代の寮は明るく清潔で快適な施設が多い
近年、寮のある学校が全国的に増えています。広島県立広島叡智学園中学校・高等学校、同じく広島にある全寮制小学校・神石インターナショナルスクール、愛知県の国際高等学校、徳島県の神山まるごと高等専門学校、イギリス式ボーディングスクールのハロウ安比校(岩手県)、ラグビー日本校(千葉県)など、多様な学校が寮を設けています。
ほかにも全国169校以上の公立高校の中から、自分の興味関心にあった高校を選択して進学するプログラム「地域みらい留学」でも、寮で生活する学校が多くあります。また大学でも、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の1年次や立命館アジア太平洋大学(APU)の国際生も1年目は寮で過ごします。
この傾向は、日本だけでなく世界的な動きになっています。イギリスの主要ボーディングスクールはアジアや中東に分校を展開し、2024年時点で44校が海外分校を持ち、2万4710人の生徒が学んでいます。多くの学校で寮が併設され、全寮制あるいは一部の生徒が寮で生活をしています。
近年の寮の増加には、学びの手法の変化が大きく影響しています。国際高校 理事長の栗本博行氏は、自身も全寮制で学んだ経験からこう指摘します。
「従来、寮は遠方からの生徒の生活拠点であり、集団生活を通じて社会的規範や自立心を育む場だった。しかし近年、寮は国際性豊かな生徒が集う多文化共生の環境へと変化し、リーダーシップを高める場へと変化している。参加者中心型学習、批判的思考と呼ばれるクリティカルシンキングなど、学びの手法が変化する中で知の総和が重視されるようになっていることも背景にある」
知の総和とは、「質×規模×アクセス」で捉えられ、「質」は知識の信頼性・関連性・汎用性など、「規模」は知識の範囲と深さ・学習共同体としてのクラス規模、「アクセス」は学習環境の距離的・経済的・言語的な利用可能性などを指します。
学校のみならず寮においても、「多国籍な環境で探究的に学ぶことが、化学反応をもたらし『知の総和』全体を押し上げることにつながる」(栗本氏)わけです。