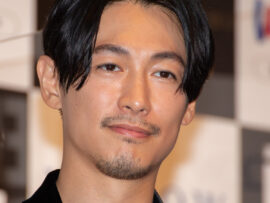近年、職場環境における新たな心理現象として「静かなカバーリング」が注目を集めています。これは、かつて話題となった「静かな退職」や「Z世代の眼差し」と深く関連しており、従業員が特定の固定観念や偏見を避けるため、自身の個人的な側面を意図的に隠す傾向を指します。特にZ世代の間で顕著に見られるこの現象は、職場の心理的安全性や個人のウェルビーイング、さらには組織全体のパフォーマンスに多大な影響を及ぼす可能性があります。
「静かなカバーリング」とは何か?その定義と実態
「静かなカバーリング」とは、従業員が職場でスムーズに溶け込んだり、昇進の機会を得るために、自身の知識不足、能力不足、あるいは個人的な特徴を隠す行為です。ソフトウェア企業Attensi(アテンシ)が2000人以上の労働者を対象に行った調査によると、この現象は現代の労働力における「静かな危機」と表現されています。調査では、回答者の58%が決めつけを避けるために自身のスキルや知識の不足を隠した経験を認め、約半数が職場で理解しているふりをしたことがあると回答。さらに40%が、進め方がわからない状況でも助けを求めない傾向にあることが明らかになりました。
コーチング専門企業Hu-Xの創業者ティア・カッツ氏は、この「静かなカバーリング」が、燃え尽き症候群や引きこもり、意欲の喪失として現れる感情的消耗である「静かな崩壊」の背景にあると指摘しています。
 職場での会議中に静かに考え込む従業員の様子。「静かなカバーリング」の概念を表す
職場での会議中に静かに考え込む従業員の様子。「静かなカバーリング」の概念を表す
ケンジ・ヨシノ教授が提唱する「カバーリング」の概念
「カバーリング」という用語は、ニューヨーク大学ロースクールのケンジ・ヨシノ教授によって提唱されました。これは、個人が固定観念、決めつけ、あるいは差別を回避するために、人種、民族、性別、性的指向、年齢、宗教、障害といった自身の特性を隠す行為を指します。労働者が職場で受け入れられ、解雇を避け、昇進するために、自身の個性の一部を隠すことはその最も顕著な例です。
ある程度のカバーリングは、多様な社会や職場でうまく適応するための自然な能力、つまり感情的知性の一部として捉えられ、ごく一般的なことです。しかし、職場で過度または慢性的にカバーリングが行われると、それは有害なものへと変化します。ストレス、燃え尽き症候群、孤立感を引き起こし、最終的には個人のウェルビーイングと組織全体のパフォーマンスの両方を著しく損なう結果となるのです。
なぜ従業員は自分を「カバー」するのか?背景と具体的な理由
Hu-Xと人材管理プラットフォームHiBobが共同で実施した調査研究では、調査参加者の97%が少なくとも何らかの形で、そして67%が頻繁にカバーリングをしていることが判明しました。その背景には複数の複雑な理由が存在します。
主な動機としては、プロフェッショナルなイメージの維持(55%)、社会的な承認欲求(48%)、差別を避けること(46%)、昇進・昇給・ボーナスの機会を高めること(46%)、年度末の業績評価で良い評価を得ること(43%)などが挙げられます。
特に、従業員が自分をカバーする傾向は、シニアリーダー(55%)や直属のマネジャー(54%)といった上位者との関係において顕著です。具体的な例としては、「チーム内で最年長であるため60歳であることを隠す」「偏見を避けるために自身の性的指向を明かさない」「注意欠如多動症(ADHD)であることを恥じ、それを隠す」「政治的見解が知られることを恐れる」「会社の義務付けた新型コロナウイルスワクチン接種を受けていないのに受けたと偽る」といった個人的な情報の秘匿行為が報告されています。
組織と個人のウェルビーイングへの影響
「静かなカバーリング」が蔓延する職場では、個人の心理的な負担が増大します。従業員は常に自己の監視下に置かれ、真の自己表現が抑制されるため、慢性的なストレスや疲労、動機付けの低下を招き、精神的健康に悪影響を与えます。これが「静かな崩壊」に繋がり、エンゲージメントの低下や離職率の上昇にもつながりかねません。
組織の観点からは、従業員が自身の強みやユニークな視点を隠すことで、イノベーションが阻害され、多様性からの恩恵を享受できなくなります。心理的安全性が低い環境では、意見の表明や問題提起が難しくなり、創造性や生産性が低下します。結果として、組織全体のパフォーマンスが低下し、競争力の喪失につながる可能性があります。
結論
「静かなカバーリング」は、個人のウェルビーイングと組織の生産性に深く関わる、現代の職場における見過ごされがちな課題です。この現象は、従業員が安心して自分らしくいられる心理的安全性に欠ける環境が根底にあることを示唆しています。企業は、多様な個性を尊重し、従業員が差別や偏見を恐れることなく、自身の能力や個性を発揮できるような、より包括的でオープンな文化を育むことが急務となっています。このような努力を通じて、従業員が生き生きと働ける職場環境を構築することが、持続的な組織成長の鍵となるでしょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース. 「静かなカバーリング」とは?Z世代が職場で見せる「眼差し」の裏側. (2024年4月11日). https://news.yahoo.co.jp/articles/4809860f269fa8ffbceeacab3e89fe425ddad5d3