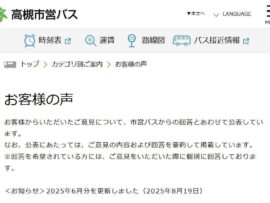11日も湿った空気の影響で大気が不安定となり、大阪府や京都府、宮崎県などで大雨警報が発表されました。近年、日本の都市部では、短時間で大量の雨が降る「都市型水害」が激化しており、大きな社会問題となっています。住宅や自動車が浸水する被害が相次ぎ、その影響は深刻です。
記録的大雨が首都圏を襲う
特に10日は、首都圏を猛烈な雨が襲いました。数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨が降った際に発表される「記録的短時間大雨情報」が、この日だけで関東地方で24回も発表される異常な状況でした。
この激しい雨の中、横浜市では10日夜、マンホールの蓋が勢いよく飛び上がり、猛烈な水が噴き出す事態が発生しました。その際、周辺の道路のアスファルト部分が割れ、飛び散った破片が近くの車3台に当たり、うち1台に乗っていた30代の母親と9歳の男の子が軽いけがを負いました。このようなマンホールからの水や空気の噴出は、昨年8月の東京・新宿駅前でも発生しており、近年相次いで報告されています。
マンホール噴出のメカニズム
水難学会の斎藤秀俊理事によると、マンホールからの噴出は主に「ウォーターハンマー現象」や「エアーハンマー現象」によるものと考えられています。激しい雨が降ると、短時間のうちに大量の雨水が下水道管に流れ込み、管内の水位が一気に上昇します。この際、中の空気が圧縮され、水圧や空気圧によってマンホールの蓋が吹き飛ぶことがあるのです。
斎藤理事は、「マンホールの隙間から水がチョロチョロと出てきたら、大爆発の前兆かもしれない」と警鐘を鳴らし、「早く、その地域から避難することが重要」と指摘しています。
 大雨による都市型水害で浸水した住宅街と治水強化の必要性
大雨による都市型水害で浸水した住宅街と治水強化の必要性
浸水被害の現実
10日の大雨では、目黒川の支流である蛇崩川の水位が急上昇し、内水氾濫が発生したとみられています。これにより、周辺地域では家屋が床上浸水や床下浸水の被害に見舞われました。
記録的な大雨から一夜明けた浸水被害の現場では、住民が片付け作業に追われていました。駐車場に止めていた車が水に浸かり、エンジンがかからなくなったため、廃車を決断した人もいます。「30年近く一緒、相棒みたいな車だった」と語る車の持ち主は、愛車に「お疲れさま」「ありがとう」、そして高台に移動させてあげられなかったことへの「ごめんね」という言葉を投げかけました。自宅が床上浸水した別の住民は、家の中に30センチメートルほど水が来た状況を語り、雨戸を閉めていても防げなかった様子を明かしました。
進む治水対策:地下調節池の役割
こうした深刻な浸水被害を未然に防ぐため、様々な治水対策が進められています。その一つが、巨大な地下調節池の活用です。
東京都港区を流れる古川では、10日午後7時頃に川の水位があふれるほどに上昇しましたが、その後わずか1時間ほどで水位はみるみるうちに低下しました。この時、行き場をなくした大量の雨水を受け止めたのが、地下40メートルに建設された巨大な調節池です。大雨で河川が増水した際に一時的に水を貯留することで、河川の氾濫や周辺地域の浸水被害を防ぐ役割を果たします。
東京都建設局の担当課長は、「こういった施設を作って運用する。さらに、増やして増強していくことが重要」と述べ、今後も都市部の治水能力強化に向けてインフラ整備を進めていく方針を示しています。都市型水害の脅威が増す中、地下調節池のようなインフラの役割はますます重要になっています。