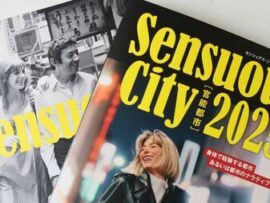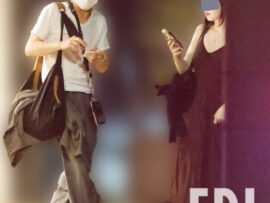宅配便の受け取り方が大きく変わる可能性が出てきた。国土交通省が、これまでオプション扱いだった「置き配」を標準とし、「手渡し」に追加料金を課す可能性について標準宅配便運送約款の改正を検討している。この一報は、日頃からネット通販を利用する多くの人々から賛否両論を巻き起こしている。背景には、深刻な物流問題、特に再配達率の削減という喫緊の課題がある。
標準宅配約款改正に向けた検討開始
国土交通省は6月26日、「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の初会合を開催した。この検討会の目的は、宅配便の再配達抑制を加速することにある。具体的な方策として、国が定めた「標準宅配便運送約款」(標準宅配約款)に「置き配」を可能とする条項を追加する改正を行う方向性が示された。
検討会は今後3回程度の会合を経て、秋頃に標準宅配約款の改正を提言する予定だ。その後、意見公募(パブリックコメント)を経て省令を改正し、早ければ2026年3月末までに約款の改正を行いたい考え。改正物流効率化法に基づき2025年4月から大手荷主などへの規制的措置が施行されるのと合わせ、宅配便に関してEC事業者や荷物を受け取る消費者の行動変容を促していく狙いがある。
再配達率削減の政府目標とその現状
政府は2023年6月に策定した「物流革新に向けた政策パッケージ」で、物流生産性向上の目安として、宅配便の再配達率を政策決定段階での12%から6%とする目標を掲げた。次いで、翌年2月に策定した「2030年度に向けた政府の中長期計画」では、2030年度までに6%まで引き下げる目標を改めて示した。この目標達成が、今回の約款改正検討の大きな動機となっている。
目標達成には至らず:最新再配達率データ
一方で、再配達率の推移を見ると、政府目標の達成は容易ではないことがわかる。宅配便大手3社(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便)のサンプル調査では、2022年10月調査時の11.8%が、2024年4月調査では9.5%となった。大手6社ベースの調査では、2022年10月時の10.6%が、2024年4月時は8.4%となっている。過去8年間は大手3社の再配達率を評価基準としていたが、より実態に近い再配達率を把握するため、大手6社の数値を基準とする方針に転換された。目標である6%には、まだ大きな開きがある現状だ。
 宅配便の荷物を玄関先に置く配達員のイメージ。再配達削減につながる「置き配」の普及が期待される。
宅配便の荷物を玄関先に置く配達員のイメージ。再配達削減につながる「置き配」の普及が期待される。
「置き配」推進の根拠:実証事業の成果
国土交通省が昨年度実施した再配達率削減緊急対策事業では、置き配やコンビニ受け取りなど、多様な受け取り方を選択した利用者にポイント還元を行う実証が行われた。その結果、置き配を実施したケースでは再配達率が最大3.1ポイント削減できるなど、置き配の有効性が確認できた。この実証結果が、置き配のさらなる普及促進を決める重要な根拠となった。
約款改正による「置き配」普及促進メカニズム
政府目標の達成に向け、再配達抑制を一層加速するためには、より多くの事業者が置き配を導入・推奨する必要がある。「標準宅配約款」が定める荷物の受け取り方に置き配の条項を加えることで、多くの宅配事業者が自社の約款に置き配を可能とする条項を追加しやすくなる。
国が定めた標準約款の中で置き配による受け取り方が認められることで、事業者は自社の約款に置き配に関する条項を記載するハードルが下がり、荷物を発送するEC事業者や、荷物を受け取る利用者に対し、置き配による配送のあり方を提示しやすくなる。これにより、国交省は置き配による受け取り方が利用者に浸透することを期待している。
過疎地域におけるドローン宅配の活用
標準宅配約款の改正では、置き配を促進する条項だけでなく、ドローンを活用した宅配の普及を加速することも盛り込まれる見込みだ。特に宅配事業者の営業所が配送エリアを十分にカバーすることが困難な過疎地域などでは、ドローンを利用する方式で配送ドライバー不足に対応するよう、自治体と宅配事業者に促していく方針が示されている。新たな技術の活用も、ラストマイル配送の効率化に向けた重要な柱となる。
検討会の構成メンバー
「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」には、学識経験者のほか、宅配関係の事業者、小売・コンビニエンスストア、EC事業者、業界団体、自治体など、幅広い関係者が参加している。主要な参加者としては、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便といった大手宅配事業者のほか、楽天グループ、アマゾンジャパンなどの大手EC事業者、全日本トラック協会、不動産協会などが名を連ねる。行政からは国土交通省をはじめ、経済産業省、農林水産省などがオブザーバーとして参加し、多角的な視点から議論が進められている。
国土交通省が進める標準宅配約款の改正は、「置き配」の標準化や、将来的には「手渡し」の有料化の可能性を示唆しており、宅配便の利用方法に大きな変革をもたらす可能性がある。これは、増え続ける宅配荷物への対応と、物流業界が直面する再配達率の高さという課題を解決するための重要な一歩と言える。検討会の議論を通じて、消費者、EC事業者、配送事業者の三者が納得できる、より効率的で持続可能なラストマイル配送の実現が目指されている。