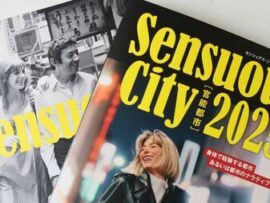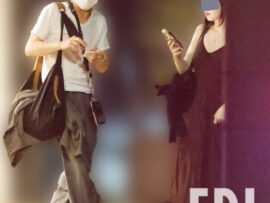参院選の前哨戦とも称された東京都議会議員選挙での参政党の躍進は、多くの政治 observers の注目を集めました。この新興政党の設立に深く関わった一人であり、早稲田大学招聘研究員および国際政治アナリストである渡瀬裕哉氏は、現在の参政党現象について独自の分析を展開しています。かつて「投票すべき政党が存在しないならば自ら創設する」という理念の下、元日本共産党国会議員秘書や YouTuber らと共に参政党を立ち上げた渡瀬氏ですが、代表である神谷宗幣氏との政策的な相違から、創設メンバーと共に党を離れる経緯をたどりました。
現在、渡瀬氏は自身のSNS上で、参政党に対して「党運営、党体制、および資金調達は評価するが、政策面は評価しない」という基本的な姿勢を示しています。また、先の参議院議員選挙で批判の対象となった「空想科学的な政策」は修正されるべきであり、「真剣に政策を立案する段階にある」との見解を表明しています。本稿では、渡瀬氏が分析する参政党躍進の理由、特にその組織構造と運営方法に焦点を当てて詳述します。
 政治集会で手を上げる熱心な参加者たち
政治集会で手を上げる熱心な参加者たち
参政党躍進を支える「新時代の政党モデル」
参政党が数多の新興政党の中から頭一つ抜け出し、既存政党の選挙基盤を脅かす存在となっているのは、決して偶然ではありません。渡瀬氏によれば、その最大の要因は、参政党が「選挙の足腰」となる「党員」を組織的に集めることに成功した政党であるという点にあります。
参政党を従来の古いタイプの政党と同じように捉えることは本質を見誤ります。渡瀬氏が強調するのは、参政党が政党運営に民間企業の経営思想やノウハウを導入した、初の試みを行っている点です。党員獲得に向けた極めて効率的かつ効果的なSNSマーケティング戦略、獲得した党員を組織活動に深くコミットさせるための独自の仕組み、そしてこれらを実現・運営するための事業主体(株式会社など)を政党が保有している structure は、これまでの日本の政党には見られなかったものです。これら統括する代表の神谷宗幣氏の優れた手腕と、組織拡大に向けた飽くなき熱意は、その成功に不可欠な要素だと渡瀬氏は高く評価しています。
既存政党との決定的な違い
参政党のモデルがなぜ革新的なのかは、既存政党と比較するとより明確になります。多くの既存政党は、親から選挙地盤を受け継いだ世襲政治家、特定の労働組合や業界団体に依存する政治家、メディアで影響力を持つタレント議員、あるいは十分な地盤を持たず経歴やルックスだけで擁立された候補者、さらには街頭や国会でパフォーマンスに終始する政治家など、様々なタイプの議員によって構成され、往々にして古い慣習や特定の既得権益に縛られています。
これに対し、参政党は、草の根で党員を集め、インターネットやソーシャルメディアを駆使して支持層を広げ、党員を組織運営の核とすることで、これらの既存の構造とは一線を画しています。これは、特定の団体や既得権益に依存しない、より民主的かつ直接的な組織運営を目指す動きと見ることができます。渡瀬氏は、このような組織形態こそが、選挙基盤が脆弱とされる中で参政党が躍進できた根本的な理由であると分析しています。
まとめ:躍進の理由と今後の課題
国際政治アナリストであり、参政党の元創設メンバーである渡瀬裕哉氏は、参政党の recent 躍進は、そのユニークな組織力と革新的な運営モデルに起因すると分析しています。民間企業のノウハウを取り入れた党員獲得・組織化戦略は、既存政党にはない「選挙の足腰」を構築しており、これが短期間での支持拡大を可能にしました。代表である神谷宗幣氏のリーダーシップも、この成功に不可欠な要素と評価されています。
しかし、渡瀬氏は組織運営や資金調達能力を高く評価する一方で、政策面には課題があるとの見解を示しています。特に参議院選挙で指摘された政策について、今後はより現実的かつ真剣な政策立案が求められる段階にあると提言しています。参政党がこの組織力を基盤に、政策的な課題を克服し、日本の政治 landscape にどのような変化をもたらすのか、今後の動向が注目されます。渡瀬氏の分析は、参政党の躍進が単なる一過性のブームではなく、「政治革命」の可能性を秘めた新時代の政党モデルの出現である可能性を示唆しています。
参照: https://news.yahoo.co.jp/articles/5067e81c4fc6124cd269b3e4db8bacf456404232