裁判官という職業は、世間一般には厳粛で地味なイメージが強いかもしれません。しかし、その冷静沈着な姿の裏には、人間としての様々な感情や願望が潜んでいます。元裁判官である井上薫氏が著書『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』で明かすように、多くの裁判官は目立たない判決に終始する一方で、中には著名な事件を通じて「スター」としての高揚感を味わいたいと願う者も少なくありません。この記事では、日本の司法制度を支える裁判官たちの、意外な「本音」と、それが職務上の制約といかに交錯するかを探ります。
著名事件と判決がもたらす高揚感:裁判官の秘めたるスター願望
裁判官の仕事の大部分は、世間から注目されることのない地道な裁判に費やされます。しかし、稀に新聞の一面を飾るような大事件、特に憲法違反などの画期的な判決を言い渡す機会が巡ってくると、裁判官は一種の「スター」になったかのような高揚感を覚えることがあります。テレビのニュースで法廷の様子が放映され、傍聴席の中央に座る裁判長が判決を朗々と読み上げる姿は、まさにその瞬間、世間の注目を一身に集める存在となります。
裁判官たちは、徹夜をしてまで懸命に判決文を書き上げます。その努力の結晶である判決が、報道陣の前で朗読され、テレビや新聞で大きく報じられることを想像するだけで、計り知れない達成感と高揚感に包まれるのでしょう。裁判官室を後にし、法廷へと向かう際には、頭の中で「ジャーン」という fanfare のような音楽が鳴り響くことさえあるかもしれません。しかし、現実は時に厳しく、法廷の扉を開けてみたら新聞記者が皆無だったという「拍子抜け」に終わることもあります。弁護団のように事前に記者クラブへ赴き、「明日の判決は非常に重要なので、ぜひ傍聴に来てください」と予告することは、裁判所としてはできません。そのため、せっかくの重要な判決が、誰の注目も浴びずに終わってしまうことに、残念な気持ちを抱く裁判官もいるのです。
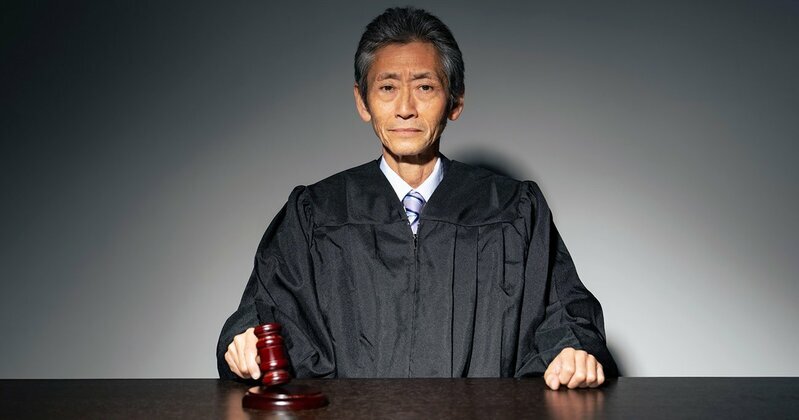 法廷で判決文を読む裁判官のイメージ
法廷で判決文を読む裁判官のイメージ
人間的な欲望と職務の制約:裁判官の多様な「顔」
裁判官の中には、判決などで目立たない地味な人生を送ることをよしとする傾向が少なからずあります。一方で、一部の裁判官が著名な判決を通じてスター気分を味わいたいと願うのは、一見すると矛盾した考え方に見えるかもしれません。しかし、この二つの願望は必ずしも相反するものではありません。多数の裁判官が存在する以上、その性格や考え方も多様であるのは自然なことです。また、事件の種類によっても、裁判官の関心やモチベーションは異なります。
著名な事件の判決言渡しで裁判長としてテレビに出たいと願うことは、決して異常なことではありません。それは裁判官の正当な職務の範囲内であり、何ら問題があるわけではありません。もちろん、裁判官の職務とは別に、私的な立場でテレビに出演し、職務にふさわしくない発言をすれば、懲戒処分などの問題が生じる可能性もあります。しかし、判決の言渡しという正当な手続きのもとで、写真撮影やテレビ録画が行われ、その様子が放送される分には、何ら悪いことをしているわけではありません。特に憲法違反を含むような重要な判決を言い渡すと、その内容はしばしば新聞のトップニュースとして扱われ、一面を飾ることが多いと言われています。
著者である井上氏自身も、カメラが法廷に導入され始めた初期の頃、写真撮影が行われ、その写真が新聞記事に掲載された経験があると言います。その際、記念にと新聞社から写真をもらったというエピソードは、裁判官もまた、自らの仕事が世に認められることに喜びを感じる一人の人間であることを示唆しています。
結論
裁判官は、その職務の性質上、常に冷静かつ客観的であることが求められます。しかし、元裁判官の井上薫氏の洞察が示すように、彼らもまた一人の人間であり、その内面には「目立ちたい」「評価されたい」といったごく自然な感情が潜んでいます。日々の地味な職務と、稀に訪れる著名事件における高揚感との間を行き来しながら、日本の司法を支える裁判官たち。彼らの人間的な側面を理解することは、司法制度そのものへの理解を深める上で不可欠です。この知られざる「本音」は、私たちが裁判官や司法制度を見る目を、より多角的で奥行きのあるものにしてくれるでしょう。
参考文献
- 井上薫『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(中央公論新社)






