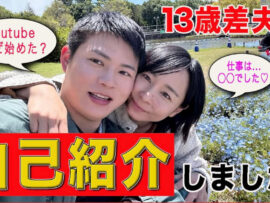7月20日の投開票が迫る参院選。全国最多の7議席を争う東京選挙区では、候補者32人の中から有力な数名が先行し、その中でも特に注目を集めているのが参政党の新人、さや氏(43)です。彼女のこれまでの活動や政策に加え、最近ロシアの政府系メディア「スプートニク」日本版でのインタビューが報じられ、大きな波紋を呼んでいます。この問題は、国内外の政治情勢とメディアリテラシーの重要性を浮き彫りにしています。
参政党さや氏の経歴と政策
さや氏は、都内の女子短大を卒業後、ジャズシンガーとして音楽活動を開始し、2008年にはCDデビューも果たしています。公式HPによると、西城秀樹さんや因幡晃さんといった著名アーティストとの共演歴もあり、そのキャリアは多彩です。さらに、FMヨコハマのラジオ番組に出演経験を持ち、現在は保守系メディアでキャスターを務めるなど、「シンガーソングキャスター」という独自の肩書で活動しています。
今回の参院選では、経済政策を主な訴えとしており、「ドケチ緊縮財政を終わらせる」「政府に足りないのは財源ではなく、国民に対する愛情」と積極財政論を主張しています。安全保障面では、日テレNEWSのYouTube番組『投票誰にする会議』で、個人的見解として「核武装が最も安上がり」と述べ、国際社会での日本の立ち位置を踏まえた核保有に言及するなど、その発言は注目を集めています。各メディアの情勢調査では、参政党が10議席以上を獲得する可能性も示唆されており、さや氏の一挙手一投足が大きな関心を集めています。
 参院選東京選挙区に立候補している参政党の新人、さや氏。
参院選東京選挙区に立候補している参政党の新人、さや氏。
ロシア政府系メディア「スプートニク」でのインタビューが波紋
さや氏は7月14日、ロシアの政府系メディア「スプートニク」の日本版「Sputnik 日本」が公開したインタビューに出演しました。このインタビューは「【参院選立候補の歌手・さや氏「政治に無関係ではいられない」】」と題され、約15分間にわたり、政治の世界への参入経緯、参政党を選んだ理由、経済と文化の関係、日本が直面するグローバリズムの波、そして日本社会の主な課題とその解決策など、多岐にわたるトピックについて語られています。
しかし、「スプートニク」は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻直後、EU(欧州連合)が虚偽情報を利用したプロパガンダを防止する目的で、圏内での配信を全面的に禁止する措置を取ったロシア系メディアの一つです。この経緯から、X(旧Twitter)上では、さや氏のインタビュー出演に対し、「参政党とロシア政府繋がってんの?」「政治を志す者であればスプートニクがロシアのプロパガンダメディアだと分かる程度の分別はあって然るべき」といった批判的な声が相次ぎ、波紋が広がっています。
参政党代表の見解とメディア出演の経緯
参政党の神谷宗幣代表(47)は、この問題に対し迅速な対応を見せました。7月15日に自身のXを更新し、さや氏がインタビューに応じた経緯について「私も広報部も許可を出していません。現場と党の末端の職員が勝手にやってしまったので、その職員には厳しい処分を下しました。これまでもこうしたことが何度もあり、私は処分を下します」と説明しました。同日に出演したネット番組「ReHacQ」でも、「スプートニクに出たから親露派はあまりに短絡的」と述べ、ロシアとの関係性を否定しています。
さらに、神谷氏は17日の投稿で、さや氏本人は「本部に確認をしている。そこはガイドライン通り」であったことを明かし、問題は「職員がなぜか独断で許可を出していた」点にあると述べました。職員にはそのような権限がないにもかかわらず許可を出したため、さや氏が出演する形になったと、党内部の管理体制に問題があったことを示唆しました。しかしながら、神谷氏がロシアとの関係性を否定する中でも、さや氏の「スプートニク」出演を問題視する声は依然として根強く残っています。
専門家が語る「スプートニク」の実態と政治家出演の問題点
この事案の背景にある「スプートニク」の実態と、日本の政治家が出演することの問題点について、明治大学サイバーセキュリティ研究所・所長の齋藤孝道教授に話を聞きました。
齋藤教授は、「我々専門家の間では、スプートニクはプーチン大統領、および大統領府第一副長官のアレクセイ・グロモフらが率いる『越境型国営メディア』という認識です。『スプートニク』も『Sputnik 日本』も母体は同じですが、欧州では『情報工作機関』という扱いでアクセスが禁止されている、完全に“アウト”とされる存在です」と解説しました。
「Sputnik 日本」の運営実態については、「“一般メディアっぽく”見せる必要があるので、基本的には政治だけではなく、生活的な話や、ほんのりとした話題など様々な軸で発信をしています。そしてフォロワーを増やす。そうした情報のなかに、発信したい自分たちの『プロパガンダ』や『ナラティブ』(特定の物語)を、所々で織り交ぜるというやり方です」と、その巧妙な情報戦略を指摘しました。
過去にも、鈴木宗男元参院議員や原口一博衆院議員など、日本の政治家が複数出演した例があることについては、「日本の政治家の間では、基本的に出演が推奨されていないメディアという認識が幅広く持たれているはずです。しかしながら、出ている先生方の中にはスプートニクがプロパガンダ機関であることをよく知らなかった可能性が高い。日本ではメディアのバックグラウンドチェックがほとんど行われていませんから、さや氏も様々なメディアから依頼が殺到するなかで、知らずに出演してしまったことも考えられる。スプートニクがインフルエンサーを起用するのは、よくあるテクニックなんです」と、背景を分析しました。
そして、日本の政治家が出演することで起こる問題点について、齋藤教授は「ロシアのプロパガンダ機関ですから、出演したことで彼らの主義・主張を補強してしまうことに繋がるんです。そうした主張に沿う発言をしていなくても、これだけ支持を集めている政党の候補者が出てしまうと、それを入り口として有権者が『スプートニク』に触れ、結果的に『スプートニク』というメディア自体の信ぴょう性を上げる可能性がある。特に参政党支持者に対して影響を与えてしまったという点において、問題だと言えるのではないでしょうか」と警鐘を鳴らしました。
結論
参政党のさや氏による「スプートニク」日本版でのインタビュー出演は、単なる候補者のメディア露出に留まらず、その背後にある「スプートニク」の性質と、それに対する日本の政治家、そして有権者のメディアリテラシーが問われる事態となりました。神谷代表が内部の不手際を認めたものの、この一件は、情報が複雑に錯綜する現代において、メディアの選定とその影響力を深く認識することの重要性を再認識させるものです。有権者が投票の判断を下す上で、候補者の発言のみならず、その情報がどのような背景を持つメディアから発信されているのか、その源泉にも注意を払う必要性が浮き彫りになったと言えるでしょう。
参考資料
- FNNプライムオンライン
- 日テレNEWS YouTubeチャンネル「投票誰にする会議」
- 神谷宗幣氏X(旧Twitter)投稿
- ReHacQ
- 時事通信
- 明治大学サイバーセキュリティ研究所