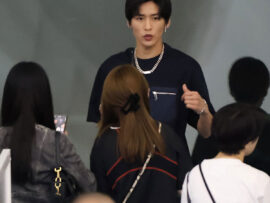2000年に導入された介護保険制度は、「介護の社会化」という理念のもと、高齢者が安心して必要な介護サービスを受けられる社会を目指して設計されました。しかし、四半世紀が経過した現在、この制度は期待とは裏腹に多くの矛盾と課題を抱え、現場と利用者の双方に大きな負担を強いています。特に、その根幹をなす「自立支援」の理念が、いつしかサービスの抑制を目的とする方向へと変質している現状は、見過ごすことのできない問題です。
「自立支援」理念の変遷:安倍元首相の発言が契機
介護保険制度における「自立支援」とは、もともと「必要なサービスを利用しながら、その人らしく生活を継続すること」を意味し、高齢者の尊厳ある生活を支えるための崇高な理念でした。しかし、この理念は近年、大きくその解釈を変えています。
その転換点の一つとなったのは、2016年11月に開催された「未来投資会議」での当時の安倍晋三総理の発言です。「これからの介護は高齢者が自分でできるようになることを助ける自立支援に軸足を置く」と述べたことを契機に、政府の会議などでも「自立支援」という言葉が頻繁に用いられるようになり、現行制度下では「サービスが不要な状態」として解釈される傾向が強まりました。これにより、介護保険からの「卒業」を促される高齢者が増加しているように感じられます。
 介護保険制度における高齢者の生活支援の様子
介護保険制度における高齢者の生活支援の様子
軽度要介護者への給付縮小と自治体への財政的インセンティブ
自立支援の理念変遷は、具体的な制度改正にも現れています。例えば、2015年の介護保険制度改正では、要支援1、2といった軽度の要介護高齢者が利用していた訪問介護や通所介護が、従来の介護保険の枠組みから外され、市区町村が実施する「総合事業」へと移行しました。これは、実質的に軽度者への給付を縮小し、サービス利用を抑制する動きと捉えられています。
さらに、2017年の法改正では、自立支援に成果を上げた自治体に対して交付金を多く配分する「保険者機能強化推進交付金」の制度が創設されました。これは、自治体に対し財政的なインセンティブを与えることで、給付の抑制を競い合わせるような状況を生み出し、サービスの質よりもコスト削減が優先される事態を招いているとも指摘されています。結果として、利用者へのサービス提供が控えられ、高齢者やその家族が必要な支援を受けられないケースが発生しています。
介護保険料の値上げとサービス制限の矛盾
昨今の社会保障費の負担増と給付削減の傾向は、介護保険制度においても顕著です。介護保険料は継続的に値上がりしているにもかかわらず、実際に受けられる介護サービスは年々制限される一方です。これは、企業が商品の価格を上げながら品質を下げるようなものであり、一般社会であれば必ず批判の対象となるでしょう。介護保険料が任意ではなく強制的に徴収されていることを考えると、この矛盾はより深刻です。
つまり、介護保険制度は「介護の社会化」を旗印にしながらも、実際には利用者負担の増大、サービスの縮小、そして介護報酬の低迷を招き、介護現場と利用者の双方に多大な負担を強いる構造へと変貌を遂げてしまっています。
結論
介護保険制度が抱えるこれらの問題は、単なる財政的課題にとどまらず、高齢者の尊厳ある生活と、それを支える介護従事者の働きがいにも深く関わる根源的な課題です。制度が本来の目的である「高齢者が安心して介護サービスを受けられる社会」を実現するためには、「自立支援」の理念をサービスの抑制ではなく、真に高齢者の生活を豊かにするための支援として再定義し、利用者のニーズに応じた適切なサービスが提供されるよう、制度全体の見直しが喫緊の課題と言えるでしょう。
参考文献
- 甚野博則『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(宝島社)