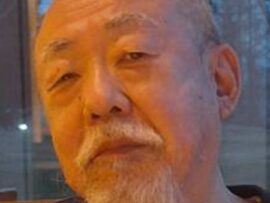国民的女優として幅広い世代から絶大な人気を誇る綾瀬はるかさんが、久々の連続ドラマ主演作『ひとりでしにたい』で、現代社会が抱える根深いテーマに挑んでいます。本作品は、伯母の孤独死をきっかけに「人生の終わり」と向き合い始める30代独身女性の姿をコミカルに、しかし深く描きます。このドラマを通して、綾瀬さん自身もまた、自身の「ひとり時間」や「死生観」、そして「より良く生きる」ためのヒントについて語っています。
国民的女優・綾瀬はるかが語る「ひとりの時間」と素顔
1985年3月24日生まれの綾瀬はるかさんは、NHK大河ドラマ『八重の桜』をはじめ、『義母と娘のブルース』、『精霊の守り人』など数々の話題作に出演し、その卓越した演技力で高い評価を得てきました。2023年には、映画『レジェンド&バタフライ』や『リボルバー・リリー』での演技が第48回報知映画賞主演女優賞を受賞するなど、常に第一線で活躍を続けています。現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、語りを担当するなど、その活動は多岐にわたります。
 国民的女優・綾瀬はるかさんが語る、飾らない「ひとり時間」の過ごし方
国民的女優・綾瀬はるかさんが語る、飾らない「ひとり時間」の過ごし方
多忙な日々を送る綾瀬さんですが、ふとした「ひとり時間」には意外な一面が垣間見えます。「広島の実家では、いつもリビングに家族が集合。寝る直前まで家族団欒タイムが続くのが当たり前だったから、大人になった今も〝ひとり〞はちょっと苦手なんです」と語る彼女。誰かと気持ちを共有したい、話し相手が欲しいという思いから、一人で出かけるときもついつい家族や友人に連絡してしまうと言います。「『なんか暑いんだけど、帰ろうかな』『それとも、もうちょっと回ったほうがいいかな』なんて、どうでもいい電話をかけてしまうんです(笑)」と、愛らしい素顔をのぞかせました。
連続ドラマ『ひとりでしにたい』への挑戦:現代社会の「死」と向き合う
久々となる連続ドラマの撮影現場で、綾瀬さんは物語が続くことによる登場人物の深まりに改めて楽しさを感じたと言います。そんな彼女が主演を務めるのが、社会派ドラマとしても注目される『ひとりでしにたい』です。
 ドラマ『ひとりでしにたい』で現代社会の「死」と向き合う綾瀬はるかさん
ドラマ『ひとりでしにたい』で現代社会の「死」と向き合う綾瀬はるかさん
本作品で綾瀬さんが演じるのは、伯母の孤独死をきっかけに自分の人生と向き合う主人公、山口鳴海。焦って婚活を始めるもののうまくいかず、ついには急に〝終活〟へと舵を切る30代独身女性の姿を、時にユーモラスに演じています。このドラマは、現代日本社会における「孤独死」や「終活」といったデリケートな問題を、視聴者にとって身近な視点から提起し、考えさせるきっかけを与えます。
30代の転機と「死生観」の変化:柄本明さんの言葉を超えて
「20代の頃は、死はとても遠くボンヤリとした存在でした」と綾瀬さんは振り返ります。当時、俳優の柄本明さんから「楽しいのは20代まで」という言葉をかけられたこともあったそうです。それは、その先には親の病気や周囲の人の死といった避けられない問題が次々と現れるからこそ、今を楽しむべきだという柄本さんのメッセージでした。しかし当時の綾瀬さんには、その言葉の真意が全くピンとこず、「ちゃんと考えずにボンヤリと20代を過ごしてしまったりして(笑)」と語ります。
そんな綾瀬さんが「人生の終わり」について真剣に考えるようになったのは30代半ばのことでした。そのきっかけは、今回演じる鳴海と同じく、身近な人の死だったと言います。「それまで何も考えてこなかったからこそ、急に未来が不安になってしまったんでしょうね」と彼女。その不安を解消するためのヒントを求め、様々な本を読み漁った結果、今回のドラマの原作である漫画と出会い、「〝あのときにこの漫画と出会っていたら〟って、初めて読んだときに思いましたもん」と衝撃を受けたそうです。
『ひとりでしにたい』が描く「より良い生き方」へのヒント
『ひとりでしにたい』というタイトルは非常に衝撃的ですが、綾瀬さんは「この作品にはよりよく〝生きる〟ためのヒントがたくさん詰まっている」と強調します。死を考えることは、責任を持って自分の人生を全うするにはどうすれば良いのか、その方法を明確にするための手がかりとなるのです。さらに、今作はこれらの重いテーマをコミカルに描いているため、観る人の気持ちを前向きにしてくれる効果があるとも語ります。
結び
綾瀬はるかさん主演のドラマ『ひとりでしにたい』は、単なるエンターテインメントに留まらず、現代社会が直面する「孤独死」や「終活」という重要な課題に対し、深く問いかける作品です。綾瀬さん自身の経験や思索を通して、私たちは「人生の終わり」を考えることが、いかに「より良い生き方」へと繋がるのかというメッセージを受け取ることができます。この作品は、多くの人々が自身の人生と向き合い、未来を前向きに捉えるきっかけとなることでしょう。
参考資料
- LEEweb via Yahoo!ニュース「【LEE COVER INTERVIEW】 綾瀬はるかさん「ひとりのわたし」」
https://news.yahoo.co.jp/articles/4917a2c3678d8e9f602dba2a9ebfdac917ca6cd4