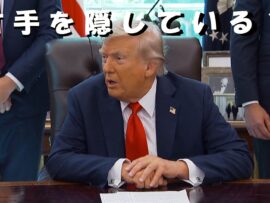食べ過ぎ、買い過ぎ、働き過ぎ、スマホの見過ぎ……。私たち現代人は、「足るを知る」という古くからの知恵を実践することが非常に困難になっています。これは、スロットマシンの設計原理にも応用されている「機会→予測不可能な報酬→迅速な再現性」という、人間のドーパミン系を強力に刺激する「欠乏ループ」が、商品やサービス、そして情報といったあらゆる分野に巧妙に取り入れられ、私たちの浪費や依存へと駆り立てているからです。本記事では、この脳に組み込まれた「欠乏ループ」のメカニズムが、いかにして現代の肥満問題と深く関連しているのかを、『満足できない脳: 私たちが「もっと」を求める本当の理由』で示された知見に基づいて解説します。
肥満増加の背景にある「食べ物」の力
1970年代以降、人類が「足るを知る」という能力を根本的に変えられてしまったかのように、肥満は驚くべき速さで増加し続けています。「肥満のパターンを見てみると、人間はこの100年間はほとんど太り続けています」と語るのは、肥満と神経科学の研究者であり、『脳をだませばやせられる 「つい食べてしまう」をなくす科学的な方法』の著者であるステファン・ギエネ氏です。「70年代、80年代、90年代、そして今日に至るまで肥満は加速しています。なぜ人間は食べ過ぎるようになったのでしょうか? 諸説ありますが、あきらかに食べ物と関係があると私は考えています」。実際、現代人に肥満が多いのは、食品産業が消費者に速く、大量のカロリーを摂取させるべく、高糖質・高脂肪の「超加工食品」を開発し、市場に供給してきた背景が大きいと指摘されています。
 現代人の肥満に繋がる超加工食品のイメージ。食品産業が大量摂取を促す製品を開発している背景を示す。
現代人の肥満に繋がる超加工食品のイメージ。食品産業が大量摂取を促す製品を開発している背景を示す。
栄養学の常識を覆すケヴィン・ホール博士の研究
1990年代後半、喫煙率の低下により減少傾向にあった心血管疾患が、肥満の増加に伴って再び増え始めていました。この問題に深く切り込んだのが、物理学のバックグラウンドを持ち、数字とデータに強い研究者ケヴィン・ホール博士です。アメリカ国立衛生研究所の研究員として、多額の資金とリソースを活用し、厳密に管理された実験を通じて、食べ物が私たちの健康や体型に及ぼす影響の核心に迫りました。
ホール博士は、従来の栄養学が炭水化物、脂肪、タンパク質、食物繊維、糖、ナトリウム、飽和脂肪といった個々の分子に焦点を当て、それらが体内でどのように処理され、どちらが高いか低いかが健康に良いか悪いかを理解することに重点を置いていたと指摘します。しかし、彼の有名な研究の一つでは、摂取カロリーが同じである限り、低炭水化物ダイエットと低脂肪ダイエットのどちらを選んでも、体重減少に統計的な差がないことが明らかになりました。これは、栄養素の比率以上に、総摂取カロリーが体重管理において重要であることを示唆していますが、それでも現代人が「食べ過ぎる」根本的な理由を解明するには、さらに脳のメカニズムに目を向ける必要があります。
脳に組み込まれた「欠乏ループ」のメカニズムとは?
「欠乏ループ」とは、「機会(cue)→予測不可能な報酬(unpredictable reward)→迅速な再現性(rapid repeatability)」というサイクルを通じて、人間のドーパミン報酬系を活性化させ、さらなる行動を促すメカニズムです。例えば、スロットマシンでは、いつ当たりが出るかわからない「予測不可能な報酬」が、ボタンを押すという「迅速な再現性」のある行動を「機会」として誘発し、ユーザーを繰り返しプレイさせます。このループは、食品産業にも巧妙に応用されています。超加工食品は、その味、食感、パッケージによって消費欲求を刺激する「機会」を提供し、食べた瞬間に脳内のドーパミンを放出させる「予測不可能な報酬」(例:想像以上の美味しさ、満腹感)を与え、さらに手軽に購入・摂取できる「迅速な再現性」を持たせることで、「もっと食べたい」という衝動を無限に引き起こします。スマートフォンの通知やソーシャルメディアの「いいね!」も同様に、このドーパミン報酬系を刺激し、依存へと導くのです。
現代社会における「足るを知る」の再考
現代人の肥満増加は、単なる個人の意志力の問題ではなく、脳の「欠乏ループ」を巧みに利用した食品産業やサービス設計が深く関わっていることが示唆されます。私たちは、絶えず「もっと」を求めるようにプログラムされた環境の中で生きており、「足るを知る」ことがかつてないほど困難になっています。ケヴィン・ホール博士の研究が示すように、個々の栄養素バランスだけでなく、私たちが置かれている食環境そのものが、過剰なカロリー摂取を促す要因となっているのです。この脳のメカニズムと社会の構造を理解することは、現代の肥満問題に対処し、より健康的で持続可能な生活を送るための第一歩となるでしょう。
参考文献
- アンナ・レンブケ(著)、櫻井祐子(訳)『満足できない脳: 私たちが「もっと」を求める本当の理由』ダイヤモンド社、2022年。