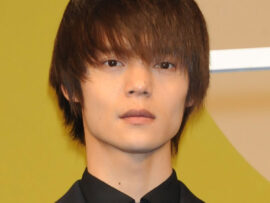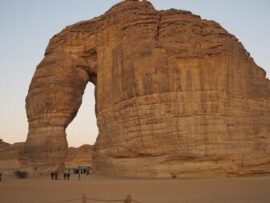台湾の最大野党である中国国民党の立法委員24人に対する大規模な解職請求(リコール)投票が26日に行われ、全ての選挙区でリコールが不成立に終わった。中央選挙委員会と台湾メディアの速報によると、いずれの選挙区でも反対票が賛成票を上回り、リコール成立はゼロという結果になった。この結果について、台湾政治の専門家である清華大学栄誉講座教授の小笠原欣幸氏が、投票までの経緯と今後の台湾政治への影響を詳細に分析した。
リコール投票結果の概要と国民党の全面勝利
今回の罷免投票は、中国国民党にとって全面的な勝利となった。今年1月以降、国民党立法委員のリコールを求める市民団体の活動が活発化し、与党である民主進歩党(民進党)もこれを積極的に支援してきた。6月上旬までは、リコール推進派が優勢であると見られていたという。
国民党は当初、リコールにはリコールで対抗する方針だったものの、有権者からの署名集めに苦戦し、党中央の指導力不足も相まって、かなり不利な状況に陥っていた。しかし、国民党の各立法委員は自らの後援会を動員し、リコール反対の小規模な説明会を各地で開催することで、徐々に体制を立て直し、反撃の準備を進めていた。
 台湾政治の専門家、清華大学栄誉講座教授の小笠原欣幸氏が、国民党立法委員に対するリコール投票結果を分析する様子。
台湾政治の専門家、清華大学栄誉講座教授の小笠原欣幸氏が、国民党立法委員に対するリコール投票結果を分析する様子。
頼清徳総統の発言が転換点に
投票結果に大きな影響を与えた転換点として、頼清徳総統の6月下旬からの発言が挙げられる。頼総統は「国家の団結」を目指し全10回の講演を開始したが、その中で「野党は濾過(ろか)されるべき不純物」と受け取られかねない発言があった。この発言は、野党支持者の強い反発と怒りを買った。
それまで一方的に攻撃される立場にあった国民党側からすると、頼総統の発言は「頼政権の好きにさせてはならない」という格好の反撃目標となった。この発言をきっかけに、終盤では各選挙区で国民党側が猛烈に巻き返し、反対票を積み上げていった。一方で、罷免支持派の活動は空回りし、勢いを失っていったと小笠原教授は分析する。
リコール派の敗北と今後の展望
リコール推進派は、最低でも6人、できれば10人の立法委員の解職を目標としていた。もしリコールが成立しなければ、その後3カ月以内に行われる補欠選挙が非常に困難になるためである。しかし、解職がゼロに終わったことで補欠選挙も実施されなくなり、リコール推進派は全面的敗北を喫した形となった。
8月23日にも中国国民党の立法委員7人に対するリコール投票が予定されているが、いずれも署名集めの段階で苦戦しており、これらのリコールが成立する可能性も高くないと小笠原教授は指摘している。今回の結果は、今後の台湾政治において、与野党間の力関係や政治戦略に大きな影響を与えるものとみられる。
今回のリコール不成立は、中国国民党にとって大きな政治的勝利であり、頼清徳総統の発言が予期せず野党支持者の結束を促した点が注目される。この結果は、今後の台湾政治における与野党間の力関係に新たな影響を与えるものとみられるだろう。