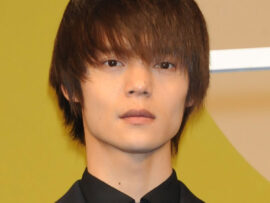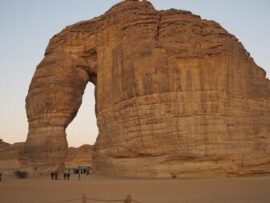源頼朝、足利尊氏、徳川家康。彼らの共通点は、いずれも「征夷大将軍」として幕府を創設し、日本の歴史において強大な権力を握った「天下人」と称されることです。この史実から、「征夷大将軍こそが唯一の天下人である」という認識が広く浸透しているのではないでしょうか。しかし、この固定観念は、必ずしも歴史的事実に即しているとは限りません。
よく知られているように、豊臣秀吉は征夷大将軍には就任せず、「関白」の地位にありながら天下を掌握しました。また、織田信長が朝廷から提示された官職の中には、征夷大将軍だけでなく、関白や太政大臣も含まれていました。これは、最高権力の称号が将軍職に限定されず、複数の形をとっていたことを示唆しています。国際日本文化研究センター名誉教授で近世史の第一人者である笠谷和比古氏は、その著書『論争 大坂の陣』(新潮選書)の中で、これらの官職の実態とその意義について詳細に解説しています。
 豊臣秀吉像と徳川家康像(模本)。征夷大将軍ではない秀吉も天下を掌握し、家康は幕府を開いたとされる権力者を象徴する。
豊臣秀吉像と徳川家康像(模本)。征夷大将軍ではない秀吉も天下を掌握し、家康は幕府を開いたとされる権力者を象徴する。
「征夷大将軍=天下人」という固定観念の問い直し
歴史に関する多くの議論において、暗黙の了解として「将軍(征夷大将軍)は唯一の天下人である」という前提が存在すると見受けられます。この想念は、徳川家康とその周辺の人々の政治的立場や、彼らが築いた政治体制を考察する際に常に影響を与え、意識的か無意識的かを問わず、人々の議論を支配する揺るぎない枠組みとして機能しているかのようです。しかし、この考え方が果たして妥当であるのか、歴史的証拠に基づいて再考する必要があります。
豊臣秀吉の関白就任と天下掌握の事実
征夷大将軍が天下人であるという認識に疑問を投げかける最大の事例の一つが、豊臣秀吉の存在です。秀吉は、武家政権の長としての征夷大将軍には就きませんでしたが、朝廷の最高位である「関白」となり、実質的に全国を統一し、天下人として君臨しました。この事実は、武士社会の統率者としての最高権力が、必ずしも将軍職に限定されないことを明確に示しています。秀吉の政権運営は、官職の持つ意味とその実際の権力構造が、必ずしも直結するものではなかったという複雑な歴史の一面を浮き彫りにしています。
織田信長に提示された「三職推任問題」の意義
この「征夷大将軍唯一説」の妥当性を問うもう一つの重要な史実が、織田信長の晩年に朝廷から提示された「三職推任問題」です。信長が朝廷の官位体系から離脱し、独自の行動を取っていることに危機感を覚えた朝廷は、彼を再び朝廷の秩序に繋ぎ止めるため、征夷大将軍、関白、そして太政大臣の三職の中から、信長が望むいずれかの職に就任するよう提案しました。
 織田信長像(模本)の一部。信長は征夷大将軍、関白、太政大臣の三職を提示され、天下人への多角的な道を提示した歴史的背景を示す。
織田信長像(模本)の一部。信長は征夷大将軍、関白、太政大臣の三職を提示され、天下人への多角的な道を提示した歴史的背景を示す。
もし征夷大将軍が唯一の天下人の職位であり、武士社会の唯一の統率者であるという認識が絶対であったならば、朝廷が信長に三職を提案すること自体が無意味であったはずです。三職の提案がなされたという事実は、当時の朝廷や貴族社会において、関白や太政大臣もまた、征夷大将軍と並び立つ形で、武士階級を統率し、天下人として君臨しうる資格を有するという共通認識が存在したことを強く示唆しています。これは、最高権力の座が単一の官職に限られていたわけではなく、複数の選択肢が存在していたという歴史的な理解を深める上で極めて重要な論点です。
結論
これまで「征夷大将軍こそが天下人である」という固定観念が広く共有されてきましたが、豊臣秀吉が関白として天下を掌握した事例や、織田信長に征夷大将軍、関白、太政大臣の三職が提示された「三職推任問題」の史実を紐解くことで、その認識は修正されるべきであると専門家は指摘しています。日本の封建時代の政治体制は、将軍職のみが絶対的な最高権力ではなかったという、より複雑で多角的な側面を持っていたのです。この歴史的考察は、現代に生きる私たちが過去の事象をより深く理解し、固定観観念に囚われずに真実を探求する重要性を示しています。
参考資料
- 笠谷和比古著『論争 大坂の陣』(新潮選書)
- 「ColBase」日本の国立文化財機関が所蔵する文化財に関する情報を提供するデータベース