なぜ現代の日本では、多くの人が「給料が上がらない」と感じているのでしょうか。その根底には、資本主義の構造と、時代と共に変遷する職業の価値観が深く関わっています。『働かないおじさんは資本主義を生き延びる術を知っている』の著者である侍留啓介氏は、極端な見方をすれば、従業員のパフォーマンスがたとえ年収1000万円に値したとしても、本人の生活が500万~600万円で賄えるならば、経営者がそれ以上を与える必要はないという、資本主義における賃金の冷徹な側面を指摘しています。この視点は、私たちの「給料」に対する常識を揺るがすものです。
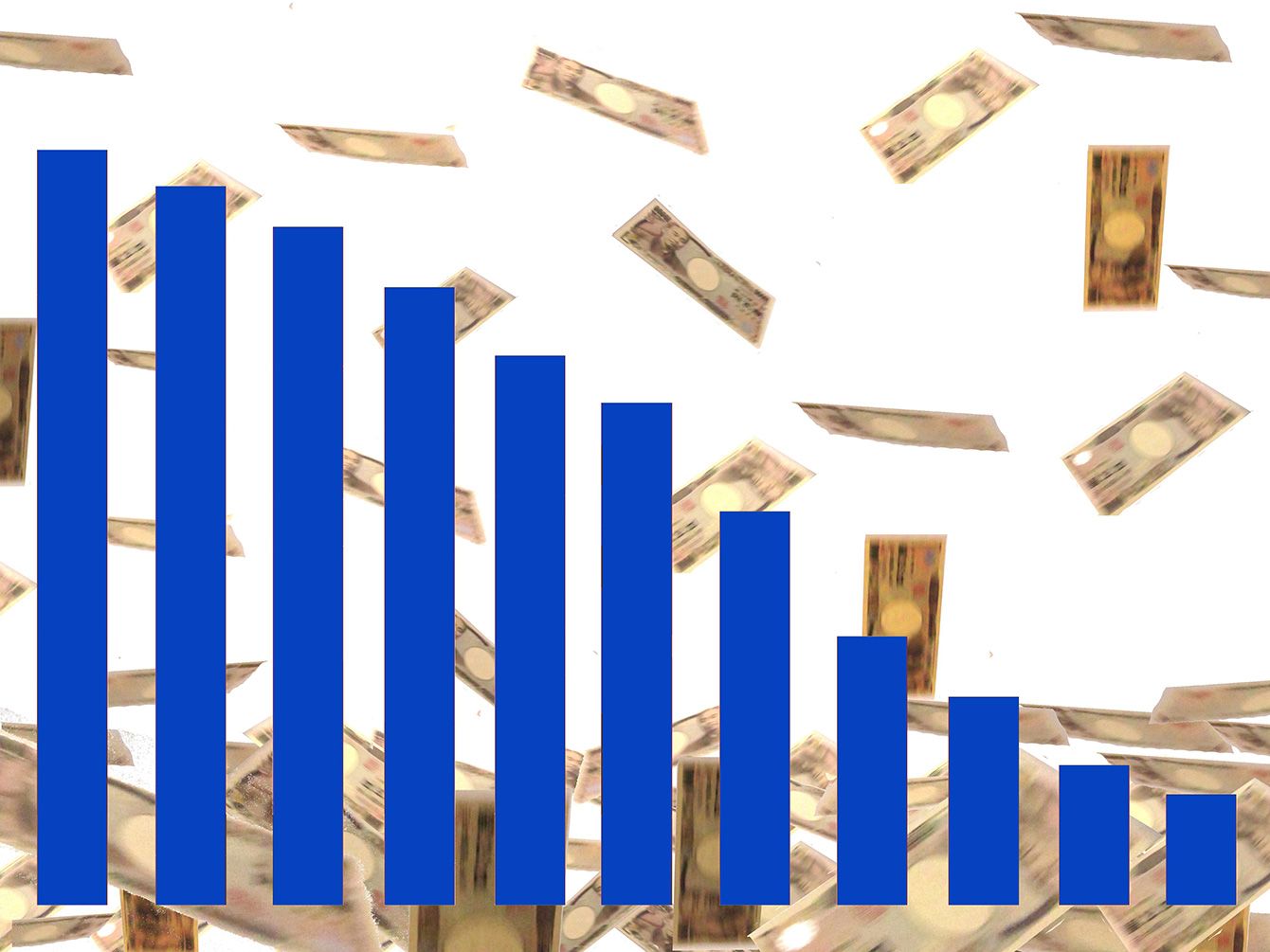 資本主義における賃金と労働の概念を示すビジネスイメージ
資本主義における賃金と労働の概念を示すビジネスイメージ
時代と共に移り変わる「勝ち組」職業の価値観
人気の職業に対する社会の評価は、時代や経済情勢によって刻々と変化します。例えば、現在の日本では外資系投資銀行に対し「なんとなくカッコいい」という印象を持つ人もいるかもしれません。しかし、この評価は決して安定したものではありません。評論家の末永徹氏が著書『メイク・マネー! 私は米国投資銀行のトレーダーだった』で綴っているように、1987年に新卒でソロモン・ブラザーズ・アジア証券に入社した際、開成高校から東京大学法学部という高学歴で外資系企業を選ぶことは非常に珍しく、周囲から奇異の目で見られたといいます。
対照的に、私が就職活動をしていた2000年代前半は、外資系投資銀行の人気が絶頂に達し、わずか数名の新卒採用枠に多くの高学歴学生が殺到していました。しかし、その人気はリーマン・ブラザーズの破綻と共に一転します。世界金融危機の余波が収まらない2010年、私がシカゴ大学MBAに留学していた頃、投資銀行出身の同級生たちは皆一様に「肩身が狭い」とこぼし、「あの業界には戻りたくない」と異口同音に語っていたのを覚えています。かつて華やかに見えた投資銀行のイメージは、リーマンショックを経て「諸悪の根源」であるかのように変わってしまったのです。このように、何が「勝ち組」とされるかは時代によって容易に変わり得るものであり、一時のイメージだけでキャリアパスを固定してしまうのは早計だと言えるでしょう。
「年収」ではなく「時給」でキャリアを語る危険性
収入それ自体をキャリア形成の目的とすることは、さらに二つの危険性をはらみます。リクルート出身で民間校長も務めた藤原和博氏は、「日本人の時給は800円から8万円くらいの幅がある。なぜ100倍もの差が生まれるのか」と問いかけ、キャリア形成において「レアキャラ」、すなわち希少性の高い人材となることの重要性を説いています。藤原氏は、「『年収』について語るとき、私は『時給』で語らなければいけないと思っています」と述べ、企業人の給与所得をアルバイトと比較します。
ここで比較の対象となっているのは、「二つのマック」です。一つは「マクドナルド」でアルバイトとして働く際の時給800円。もう一つは「マッキンゼー」のシニアコンサルタントの報酬を時給換算した8万円です。「マクドナルド」も「マッキンゼー」も、日本ではともに「マック」という通称で親しまれています。藤原氏の見解には頷ける部分も少なくありません。給与に限らず、資本主義の市場ではあらゆる価値が希少性、つまり藤原氏の言う「レアキャラ」であることによってもたらされるからです。しかし、実際にマッキンゼーで働いた経験を持つ者として、この主張には多少の無理があるようにも思えます。高付加価値な仕事の場合、投入した時間と成果が常に比例するわけではなく、またその評価も単純な時給換算では捉えきれない側面があるからです。
まとめ
私たちの給料が上がらない根本的な理由の一つは、資本主義において賃金が「生活を賄うため」という側面を持つことにあります。そして、時代と共に変化する「勝ち組」職業の価値観を理解し、一時の流行に流されないキャリア形成の視点を持つことが重要です。藤原和博氏が提唱する「時給」と「レアキャラ」の概念は、自身の市場価値を高める上で示唆に富んでいますが、高額な報酬を伴う専門職においては、単純な時間単価でその価値を測ることは難しい場合もあります。労働市場における自身の価値を最大化するためには、多角的な視点からキャリアと収入の関係性を捉え、常に希少性と専門性を追求する姿勢が求められるでしょう。






